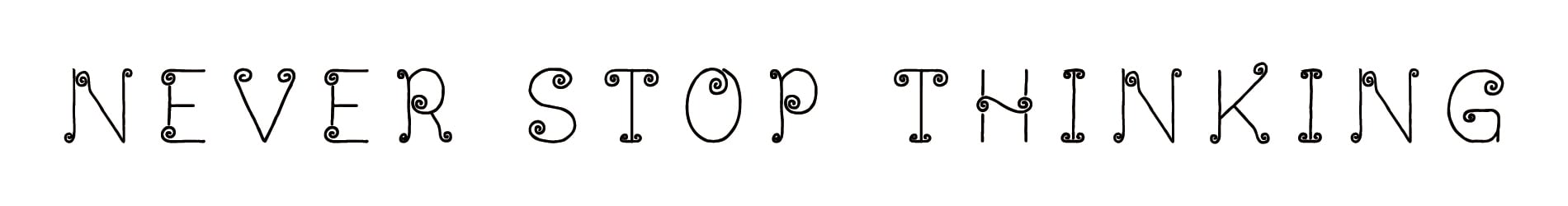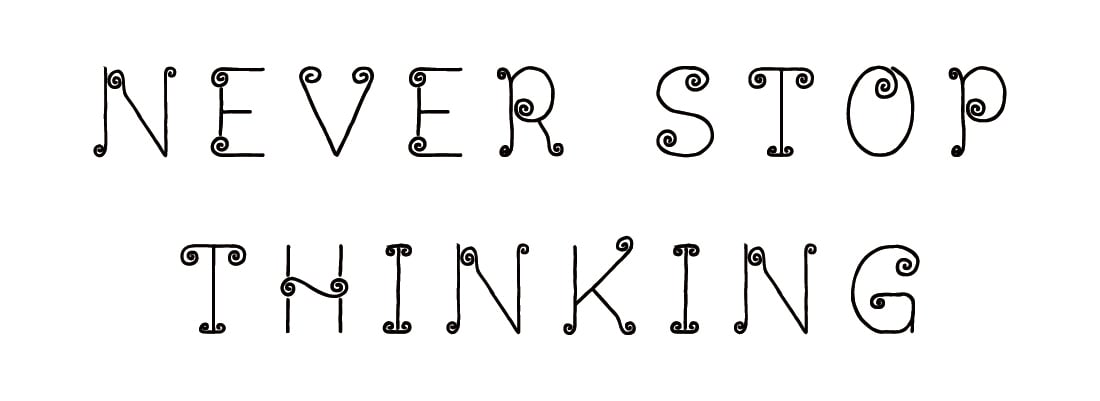-

弾劾可決の日を歩く "私たちはいつもここにいた”|岡本有佳
¥1,100
[版元サイトより引用] 2024年12月3日、尹錫悦大統領による突然の「非常戒厳」宣布から始まった韓国の混乱。大統領弾劾を求め200万人規模のデモが行われ、大勢の若い女性たちが参加した。多くの市民が立ち上がり声を上げる根底にあったのは、尹政権の言論弾圧や不正、アンチフェミニズム政策への怒り。現地を取材し、抵抗する人々の声を聞いた記者による、韓国の現実。 より尖がった、踏み込んだコンテンツを発信するレーベル「gasi editorial」第7弾! 目次 はじめに ソウル・弾劾可決の日を歩く 家の中で大切な、一番明るい光を持って集まった女たち イ・ラン インタビュー「私たちはいつもここにいた。見てなかっただけ」 言論弾圧に抗う① 独立メディア ニュース打破 言論弾圧に抗う② メディアを監視する 民主言論市民連合 韓国の若い女性たちはなぜデモに行くのか−−怒りとフェミニズム 趙慶喜 岡本有佳 記者/編集者として活動する。女性たちの表現活動やメディア問題のほか、日本軍「慰安婦」問題などにも関心がある。共編著『《自粛社会》をのりこえる』(岩波ブックレット)、『政治権力VSメディア 映画『共犯者たち』の世界』(夜光社)など。 [書籍情報] 編著:岡本有佳 サイズ:128mm×182mm 製本:並製 ページ数:68ページ
-

100年先の憲法へ 『虎に翼』が教えてくれたこと|太田啓子
¥1,540
[版元サイトより引用] あの朝ドラを読み解けば憲法がわかる? みんなの「はて?」にこたえる入門書 熱い反響を呼んだNHKドラマ『虎に翼』を題材に、『これからの男の子たちへ』(大月書店)で知られる著者が、憲法の基礎を紙上レクチャー。 100年前の女性たちから現代に託されたメッセージとは? ジェンダー平等を阻害しない「これからの」男性像とは? “虎翼愛”全開で語り尽くします! 目次 第1部 『虎に翼』が教えてくれた憲法 憲法を主人公にしたドラマ『虎に翼』 そもそも憲法って何? 憲法は国民から国への命令(立憲主義) 敗戦によって書き込まれた「基本的人権」 多数決で決めた法律でも侵害できない権利 従いたくない法律を変えるには? 尊属殺をめぐる違憲判決の例 憲法は少数者の権利のためにある 三淵嘉子が辿った茨の道 憲法24条と民法改正 ベアテから日本女性たちへの贈りもの 家制度をめぐる論戦とシスターフッドのリレー 「個人として尊重」される権利と同性婚訴訟 「あげた声は決して消えない」――「不断の努力」の大切さ [寄稿] 「はて?」の想いをつなぐ場に 三淵邸・甘柑荘保存会 上谷玲子 第2部 男性たちの群像 1 花岡と轟――「感情の言語化」とホモソーシャルの克服 花岡の建前と隠された本音 「思ってもないことを宣うな」 轟の変容 2 優三――「ケアする男性像」と対等な関係性 男らしさの三つの要素―優越志向・権力志向・所有志向 優三が見せた別の強さとケア能力 ギンズバーグ判事を支えたケア力が高い夫 3 小橋――「マジョリティ男性」の変化の歩み 感情の言語化 男性裁判官たちの友情 「平等な社会の邪魔者にはなりたくない」――ミソジニーとの決別 それでも、「男もつらいよ」では終わらない 4 穂高先生――「リベラルな理解者」の二つの顔 「続けて」が示す傾聴力 寅子の怒りはなぜ届かなかったのか 民法改正案審議会での再会 少数意見になることを恐れない 寅子が花束贈呈を拒否した理由 あとがき [書籍情報] サイズ:128mm×188mm 製本:並製 ページ数:160ページ
-

自分の言葉で社会を変えるための 民主主義入門|フィリップ・バンティング
¥1,980
[版元サイトより引用] あなたの〈声〉が大事な理由、知ってる? なにを言うか、どう言うかには、世界を変える力がある。民主主義の基本と歴史、そして自分の考えを伝えるための方法を知る、一番やさしい入門書。 [書籍情報] 著:フィリップ・バンティング 訳:堀越英美 サイズ:215mm×265mm ページ数:34ページ
-

若者の戦争と政治 20代50人に聞く実感、教育、アクション
¥1,870
[版元サイトより引用] むしろ「学ばなかったこと」のほうが印象深いかも(26歳) 「先生だから政治的意見は言えない」と、"中立"であることにこだわっていたのが印象的(23歳) 「社会や政治に無関心な若者」は、こうして生まれたー 1994〜2004年生まれ、20代50人に聞いた、戦争と政治。 「慰安婦」の文字が教科書から消され、戦争における加害の歴史を学ばなかった。 性教育がバッシングされ、激しいジェンダーバックラッシュが起こった。 生きづらさを自己責任で丸め込まれ、「ゆとり」や「さとり」と後ろ指をさされる。第2次安倍政権下で義務教育期を過ごしたかれらは、当時の政治や教育にどう影響され、何を感じてきたのか。 生まれ育った1994〜2024年の政治、教育、文化、社会の動きを年表で振り返るとともに、若者たちの声を聞く1冊。 戦争を起こさないようにするのは誰か。問われなければいけないのは政治だ。(寄稿 武田砂鉄) 戦争や政治と聞いた時、どんなものを思い浮かべますか? 小学校〜高校までに学んだ戦争、政治について、印象に残っていること、記憶していることを教えてください。 戦争 日露戦争とか、日清戦争などの単語と年号。受験頻出のことばかり覚えている。なんで起こったのかとかは覚えていない(23歳) 土地や資源を奪い合って人が死ぬ行為、ぐらいの想像力しか持てない(24歳、男) 「慰安婦」という言葉は教科書にも書かれていなかったし、聞いたこともなかった(26歳) 日本が受けた被害については印象に残っているのに、日本が他の国や地域に対して行ってきたことについてはさらりと済まされていたような気がします(28歳) 政治 腐敗だらけでゴミだけど、世の中も同じくらいダメなところがあるから、変えようがないもの。「お上」。中高年男性。居眠り(22歳) 政治についていくにはエネルギーが必要で、日々の生活に精いっぱいのときには簡単ではない(22歳) 選挙権を得た年に、有権者として初めて公約をチェックした際、自分の住んでいる地域では若者にとって魅力的な候補者がほとんどいないことに驚きました(26歳) 政治についてもっと声を上げていい、批判して、何なら怒ってもいい、私たちにはその権利があるということをもう少し早く知っておきたかった(29歳) (回答より) [書籍情報] サイズ:112mm×173mm 製本:並製 ページ数:232ページ
-

有権者って誰?|藪野祐三
¥880
[版元サイトより引用] 選挙権年齢が18歳に引き下げられ、中高生に向けた主権者教育が求められています。本書は、若い世代が自らを選挙の当事者として考えるきっかけとなるように「有権者」を切り口に、選挙のしくみや意義をわかりやすく解説します。有権者には何が求められているのか、社会に参加するとはどのようなことなのかを学ぶための一冊です。 目次 はじめに 第1章 有権者には4つのタイプがある 1 市民には4つのタイプがある 2 有権者にも4つのタイプがある 3 それぞれのタイプを評価してみる 4 あなたはどのタイプ? 第2章 浮動票という言葉が使われた時代があった 1 時代を振り返ってみる 2 政党や政治は利益誘導を基本とする 3 有権者の支持政党はあまり変化しなかった 4 浮動票に変化が現れた 第3章 無党派層が現代日本の政治を支配している 1 有権者の支持政党は固定化しなくなった 2 政党も多党化してきた 3 受け皿が欲しい 4 あなたも無党派ですか 第4章 有権者をとりまく社会は流動化している 1 教育は流動化している 2 居住地の流動化が始まった 3 社会は急激に個人化している 4 「コンビニ文化」で地域は同質化している 第5章 選挙の前に足元の社会を知る 1 無知に気づく 2 地域を学ぶ 3 地域の課題に出会う 4 投票のすすめ あとがき [書籍情報] サイズ:105mm×173mm ページ数:160ページ
-

自分ごとの政治学|中島岳志
¥737
[版元サイトより引用] もっとも分かりやすい、著者初「政治」の入門書! 学校で教わって以来、学ぶ機会がない「政治」。大人でさえ、意外とその成り立ちや仕組みをほとんんど知らない。しかし、分かり合えない他者と対話し、互いの意見を認め合いながら合意形成をしていく政治という行為は、実は私たちも日常でおこなっている。本書では、難解だと決めつけがちで縁遠く感じる「政治」の歴史・概念・仕組みが2時間で理解できる。政治の基本概念は、どのように私たちの生活に直結しているのか。自分なりに政治の「よしあし」を見極めるポイントはどこにあるのか。「右派と左派」「民主主義」から「税金と政策」まで。思わず子供にも教えたくなる、政治と自分の「つながり」を再発見するための教養講義。 [書籍情報] サイズ:148mm×210mm ページ数:112ページ
-

選挙との対話
¥1,980
[版元サイトより引用] 紹介 日本の選挙の科学的なデータ分析に加え、杉並区長へのインタビューやお互いの話を聴き合いながら思索を深める哲学対話から、選挙を、そして政治をより身近にたぐり寄せるためのさまざまなヒントをちりばめた、すべての世代に向けた選挙の新しい入門書。 解説 「あなたにとって選挙とは?」 「政治参加の手段?」「民主主義の根幹?」、 それとも「行っても/行かなくても変わらないもの……?」 近年、国内外を問わず、選挙のあり方そのものが問われる事態が相次いで起こっている。こうした状況のなかで、選挙に関して「科学的に」わかっていることはなんなのか。またそれを知ることは、私たちの生活にどのように関係してくるのだろうか。 2009年以降、自民党の勝利が続く日本の国政選挙について、政治学やデータ分析の専門家たちはどのように見ているのか。国際的にみて女性の社会進出が遅れているといわれている日本の現状は? またそれを取り巻くメディアの状況は? そして、若い世代が感じている日本の選挙のリアルとは? 科学的な分析に加え、杉並区長へのインタビューやお互いの話を聴き合いながら思索を深める哲学対話から、選挙を、そして政治をより身近にたぐり寄せるためのさまざまなヒントをちりばめた、すべての世代に向けた選挙の新しい入門書。 目次 まえがき 荻上チキ 第1章 なぜ自民党は強いのか?――政治に不満をもつのに与党に投票する有権者 飯田 健 1 自民党の強さ 2 自民党の強さの原因 3 政治に不満をもつにもかかわらず自民党に投票する有権者 4 自民党が負けるシナリオ? 第2章 選挙制度は日本の政治にどう影響しているのか?――自民党一党優位の背景を説明する 菅原 琢 1 自民党の「強さ」の謎 2 もくろみが外れた衆院選挙制度改革 3 小選挙区比例代表並立制が促す終わらない政界再編 4 並立制の解は政党間の協力 5 自民党一党優位は絶対ではない 第3章 なぜ野党は勝てないのか?――感情温度や政党間イメージについて 秦 正樹 1 「野党はふがいない」と言われ続ける理由 2 世論の野党への認識:1――感情温度を用いた分析 3 世論の野党への認識:2――イデオロギーを用いた分析 4 世論の野党への認識:3――政権担当能力評価 5 野党の今後を考える 第4章 なぜ女性政治家は少ないのか?――政治とジェンダー、政治家のメディア表象について 田中東子 1 新聞はどのように女性政治家を報じてきたのか 2 ポピュラー文化と女性リーダーの表象 3 「すべての女性たち」が政治の場で活躍できる社会とは 第5章 政治家にとって対話とは何か?――杉並区長・岸本聡子インタビュー 岸本聡子(聞き手:永井玲衣/荻上チキ) 第6章 私たちはどうやって投票先を決めているのか?――日本の有権者についてわかっていること、データからわかること 大村華子 1 私たちの投票は何によって決まっているのか 2 日本の有権者の投票は何によって決まっているのか 3 データを使ったら、どんなことがわかるのか 第7章 私たちにとって選挙とは何か?――選挙をめぐる哲学対話 永井玲衣/荻上チキ あとがき 荻上チキ [書籍情報] 編著:荻上チキ 企画:社会調査支援機構チキラボ 著:飯田 健、菅原 琢、秦 正樹、田中東子、岸本聡子、大村華子、永井玲衣 サイズ:148mm×210mm 製本:並製 ページ数:180ページ
-

言いたいことが言えないひとの政治学|岡田憲治
¥1,980
[版元サイトより引用] 「給料上げてと会社に言いたい」 「暴言やめてと老親に言いたい」 「戦争やめろと世界に言いたい」…… じっとガマンするのでも、ガツンと言ってやるのでもない―― 人生を自分でつくっていく、大人のための対話術 家庭でも職場でも地域社会でも、ふつうに生活しているだけで、私たちは他者との不和やトラブルに悩まされる。言いたいことは溜まるけど、そうそう言えないのが大人の世界……。主張や発言ができないのなら、黙って我慢するしかないのか。 そんなわけない、と政治学者の著者は断じる。ほどよく交渉したり、提案したり、説得したり……ふだんづかいの対話術を、政治学の知恵をつかって考えていく。個人・集団・社会にたいして、自分の思いを届ける技法とマインドをユーモアたっぷりに惜しみなく提案する一書。 「いろいろな人間がいるこの世界で心の異音が大きくなった時、「言う/言えない」の二つに一つの選択肢しかないということはやはりないのだ、ということです。「言う」と「言わない」の間には、広大なエリアがある……そのことをみなさんは知らない、いや「忘れている」のです」(本書より) 目次 理論編 第1章 「声を上げよう!」と言われても 言いたいことはそうそう言えない 「ちゃんと言いなよ」がもたらすもの 「沈黙してはならない」と伝えた理由 正論で世界を変えることが難しくなった 名づけられようもない生活者 言えない理由を切り分けてみる 自分の気持ちをつかめないから 波風が立つのが嫌だから 角が立つと面倒くさいから 圧力や制裁が怖いから 孤立するかもしれないから 第2章 「言う」ための技法 「言う」と「黙る」の間にあるもの 着地点はどこか? 言い方はたくさんある――工夫しながら言ってみる 勇気を出す 言い方を工夫する――毅然と言う/丁寧に言う/お願いするように言う/静かに言う 目的に重心をかける――ぶつける/示唆する/頼りにする/探り尋ねる 沈黙してみる 第3章 「やる」ための技法 「言う」だけでなく「ふるまい」もある 主張できることが貴重だった過去 「私たちの物語」が成立していた時代 個人へとミクロ化する「言う」という行為 ふるまいの技法もたくさんあ 勝つ――対処可能な範囲に収める/仲間にしてしまう 勝たないが負けない――負け越しを受け入れる/捕まえておく/引き延ばす 助けを求める――仲間をつくる/事態を公開する 言ったりやったりしている人を孤立させない――頑張る人たちの話を聞いてあげる/プロセスを記録してあげる/頑張る人たちを励ましてあげる 逃げる・諦める 実践編 第1章 ネトウヨになった父に暴言はやめてと言いたい 第2章 「男なら泣くな」と子どもを叱る夫に言いたい 第3章 マンション管理組合の長老に「話を聞いて」と言いたい 第4章 PTA活動で「ムダな仕事は省こう」と言いたい 第5章 会社に給料を上げてほしいと言いたい 第6章 子どもに「ダメなやつ」と言った担任の先生と学校に言いたい 第7章 近隣外国人に生活マナーを守ってほしいと言いたい 第8章 地域イベントをやってみようと言いたい 第9章 多様な選択肢をつくってと政治に言いたい 第10章 戦争をやめてと世界に言いたい [書籍情報] サイズ:128mm×186mm 製本:並製 ページ数:272ページ