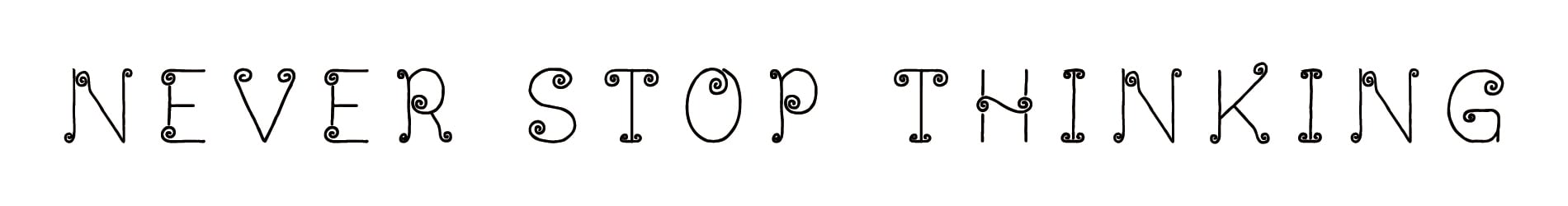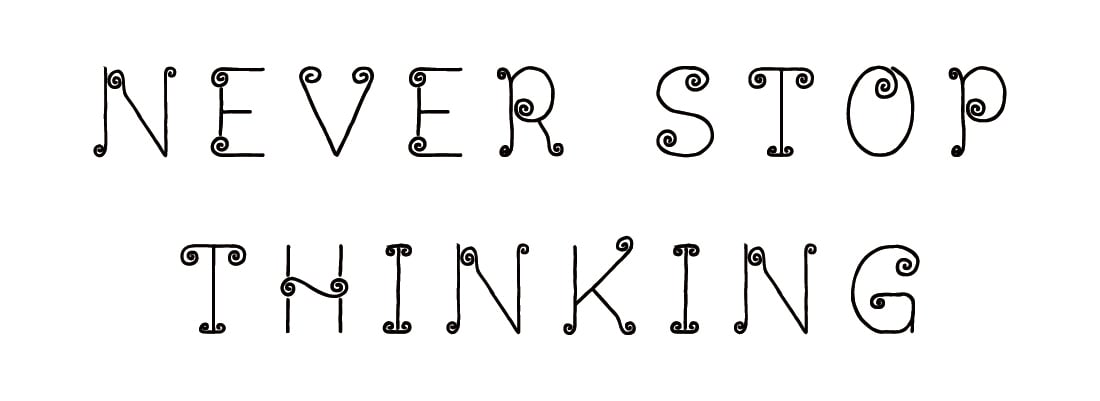-

Drop for Palestine|はまち乃藍
¥1,500
[版元サイトより引用] 「パレスチナでの停戦まで休載する」と決めた人気漫画家、自分の平穏な日々を守るため政治的なコンテンツから距離を置いている人、職場のノンポリな人にパレスチナの話をしてみようと試みる人、国際ストライキの日に授業をストライキすることを決めた学生。それぞれの人物を通して描かれるパレスチナと私たちの「日常」の話。 [書籍情報] サイズ:148mm×210mm ページ数:96ページ
-

見知らぬ人を認識する パレスチナと語りについて|イザベラ・ハンマード
¥2,970
[版元サイトより引用] 「その場にいない私たち、遠くからただ見守るしかない私たちは、これに耐えようと自分の感情を切り離すとき、どのように自分自身を深く損なっているのだろうか」 ジェノサイドが行われているガザ。そこには、人間を人間として見ないという認識の暴力が並走している。そうした認識が変わらないかぎり、暴力は続いていく。 小説は、私たちの認識が変わる瞬間を描いてきた。他者の光とともに、見えなかった現実が姿を現す。 パレスチナ系英国人の作家が、サイードを手がかりに、現在進行中の暴力を支える認識の転換の瞬間をうながす。他者を非人間化することで自分が人間であるとする植民地的認識が崩れることで、ともに抵抗し、ともに支えあうための行動を起こす道が開かれる。岡真理による解説「ホロサイドに抗して」を付す。 [書籍情報] 著:イザベラ・ハンマード 訳・解説:岡真理 サイズ:135mm×195mm ページ数:152ページ
-

パレスチナを破壊することは、地球を破壊することである|アンドレアス・マルム
¥3,300
[版元サイトより引用] 「資本主義の「中心」は、暖炉に燃料をくべ続け、ガザに爆弾を運び続けている」 1840年、イギリス帝国はパレスチナの港町アッカーを粉砕した。それは、石炭で駆動する蒸気船が世界ではじめて大規模に投入された瞬間だった。パレスチナへの連帯とは、化石資本主義と入植者植民地主義というふたつの歯車を止めることであり、沸騰状態にある地球を救うことである。化石燃料とその利益を至上のものとするシステムのもと、破壊と粉砕をもたらすグローバルな構造的暴力「ビジネス・アズ・ユージュアル」の歴史と本質に迫る、いま必読の書。 目次 序文 無制限(ノー・リミット) パレスチナを破壊することは、地球を破壊することである 初めての先進後期資本主義ジェノサイド 粉砕様式 わが国には貴国を粉砕する力があると心得よ 粉砕されたアッカー 支配下に置かれたエジプト 引き渡されるパレスチナ 出来事ではなく構造 諸段階からなる二重破壊 化石イスラエル ガザの燃焼 ロビー説を論駁する パレスチナと地球を破壊するものを破壊すること ブルジョワジーの冷酷さの典型例 最初のテクノジェノサイド レジスタンスは続く パレスチナ抵抗組織(レジスタンス)に関するいくつかの異論への反論 抵抗組織(レジスタンス)の左側で 個人的な覚え書きについて 化石燃料を利用するパレスチナ、利用しないパレスチナ 入植者の殺害について 現存するハマースについて 誓いを守る 戦士を非難することについて イスラエル・ロビー説への異論に対する反論 原注 補論 タンクの壁を叩く― パレスチナの抵抗について(訳=中村峻太郎) 訳者あとがき [書籍情報] 著:アンドレアス・マルム 訳:箱田徹 サイズ:130mm×190mm ページ数:232ページ
-

イスラエルについて知っておきたい30のこと|早尾貴紀
¥2,090
[版元サイトより引用] 2023年10月7日に起きたハマースの蜂起から約15カ月半後の2025年1月19日、イスラエルとハマースの間で6週間の「停戦」合意がなされた。イスラエルの一方的な爆撃によりガザ地区の公共施設や主要インフラは壊滅的な状況に陥り4万人超が死亡、その大半は子どもや女性だったとされる。 だが、イスラエルによる暴力はいまに始まったことではない。1948年のイスラエル建国前からシオニストたちはパレスチナの地の略奪を目標に、欧米や周辺諸国を巻き込み、暴力を繰り返してきた。 キリスト教福音派のシオニズムへの接近、ホロコーストの政治利用、ユダヤ教とシオニズムの対立、PLOの挫折、オスロ合意の欺瞞、〈10・7〉蜂起、そしてイスラエルが描く「ガザ2035」の未来図とは? いま私たちがパレスチナ問題を考えるための基本書。 「停戦」は、一般的な国家戦争の停戦とは全く異なり、イスラエルによる一方的なガザ地区でのジェノサイドの「一時停止」にすぎません。ガザ地区の占領も封鎖も変わらず、またやはり占領下のヨルダン川西岸地区で続いているイスラエル軍の侵攻と入植者による襲撃・収奪も止まることがないのです。――「あとがき」より 目次 前史|ユダヤ人はなぜ差別されてきたのか 第1部|19世紀~1948年| イスラエルはどのようにしてつくられたのか 1.シオニズムはどのように誕生したのか 2.植民地主義とシオニズムの関係とは 3.シオニズムの物語とは 4.イスラエルはどのように建国されたのか(1) 5.イスラエルはどのように建国されたのか(2) 6.イスラエルはどのように建国されたのか(3) 7.国際社会の責任とは 8.イスラエル建国に対する世界の思想は 第2部|1948年~90年代| イスラエルはどんな国か――占領政策、オスロ合意まで 1.建国されたイスラエルはどんなところか 2.イスラエルの産業とは 3.イスラエルには誰が住んでいるのか 4.イスラエルはどのように国民統合を図ったのか 5.ホロコーストと宗教の利用 6.1967年以降の占領政策とは 7.パレスチナの抵抗運動とは 8.オスロ合意とはなにか(1) 9.オスロ合意とはなにか(2) 10.オスロ合意に対する世界の思想は 第3部|2000年代~| オスロ合意後のイスラエルはどうなっているか 1.第2次インティファーダ後の一方的政策とは 2.イスラエルはなぜハマースを敵視するのか 3.パレスチナの民意へのイスラエルの反応は 4.〈10・7〉蜂起とは 5.〈10・7〉とは何だったのか 6.ガザ侵攻でなにか起きているのか 7.ガザ侵攻でイスラエルが得る利益とは 8.イスラエル国内でのガザ侵攻の受けとめ方は 9.イスラエルはガザ侵攻後をどのように考えているのか 10.世界の反応は 11.ガザ侵攻に対する世界の思想は 12.私たちになにができるのか [書籍情報] サイズ:128mm×188mm ページ数:256ページ
-

とるに足りない細部|アダニーヤ・シブリー
¥2,200
SOLD OUT
[版元サイトより引用] 1949年8月、ナクバ(大災厄)渦中のパレスチナ/イスラエルで起きたレイプ殺人と、現代でその痕跡を辿るパレスチナ人女性。二つの時代における極限状況下の〈日常〉を抉る傑作中篇。 この作品の「細部」に宿っているものは、私の精神世界を激しく揺さぶり、皮膚の内側を震えさせる。この本の中の言葉の粒子に引き摺り込まれ、永遠に忘れられない体験になり今も私を切り刻んでいる。 ——村田沙耶香氏(作家) かき消された声、かき消された瞬間と共にあるために、この小説は血を流している。 ——西加奈子氏(作家) *2023年、本作はドイツの文学賞であるリベラトゥール賞を受賞。しかし同年10月、イスラエルによるガザへの攻撃が激化するなか、フランクフルト・ブックフェアで開催予定だった授賞式は同賞の主催団体リトプロムによって中止され、ブックフェアは「イスラエル側に完全に連帯する」との声明を出した。この決定に対しては、作家や出版関係者を中心に、世界中から抗議の声が上がっている。 [書籍情報] 著:アダニーヤ・シブリー 訳:山本薫 サイズ:130mm×188mm ページ数:168ページ
-

ガザとは何か パレスチナを知るための緊急講義|岡真理
¥1,540
[版元サイトより引用] 緊急出版! ガザで何が、なぜ起きているのか。歴史的文脈とポイントを平易に解説する「まずここから」の一冊 2023年10月7日、ハマース主導の越境奇襲攻撃に端を発し、 イスラエルによるガザ地区への攻撃が激化しました。 長年パレスチナ問題に取り組んできた、 パレスチナ問題と現代アラブ文学を専門とする著者が、 平易な語り口、そして強靭な言葉の力によって さまざまな疑問、その本質を明らかにします。 今起きていることは何か? パレスチナ問題の根本は何なのか? イスラエルはどのようにして作られた国? シオニズムとは? ガザは、どんな地域か? ハマースとは、どのような組織なのか? いま、私たちができることは何なのか? 今を知るための最良の案内でありながら、 「これから私たちが何を学び、何をすべきか」 その足掛かりともなる、 いま、まず手に取りたい一冊です。 本書は、10月20日京都大学、10月23日早稲田大学で開催された緊急セミナーに加筆修正を加えたものです。 目次 第1部 ガザとは何か 4つの要点/イスラエルによるジェノサイド/繰り返されるガザへの攻撃/イスラエルの情報戦/ガザとは何か/イスラエルはどう建国されたか/シオニズムの誕生/シオニズムは人気がなかった/なぜパレスチナだったのか/パレスチナの分割案/パレスチナを襲った民族浄化「ナクバ」/イスラエル国内での動き/ガザはどれほど人口過密か/ハマースの誕生/オスロ合意からの7年間/民主的選挙で勝利したハマース/抵抗権の行使としての攻撃/「封鎖」とはどういうことか/ガザで起きていること/生きながらの死/帰還の大行進/ガザで増加する自殺/「国際法を適用してくれるだけでいい」 第2部 ガザ、人間の恥としての 今、目の前で起きている/何度も繰り返されてきた/忘却の集積の果てに/不均衡な攻撃/平和的デモへの攻撃/恥知らずの忘却/巨大な実験場/ガザの動物園/世界は何もしない/言葉とヒューマニティ/「憎しみの連鎖」で語ってはいけない/西岸で起きていること/10月7日の攻撃が意味するもの/明らかになってきた事実/問うべきは「イスラエルとは何か」/シオニズムとパレスチナ分割案/イスラエルのアパルトヘイト/人道問題ではなく、政治的問題 質疑応答 ガザに対して、今私たちができることは?/無関心な人にはどう働きかければいい?/パレスチナ問題をどう学んでいけばいい?/アメリカはなぜイスラエルを支援し続けるのか?/BDS運動とは何? 付録 もっと知るためのガイド(書籍、映画・ドキュメンタリー、ニュース・情報サイト) パレスチナ問題 関連年表 [書籍情報] サイズ:128mm×188mm ページ数:208ページ
-

中学生から知りたいパレスチナのこと|岡真理 小山哲 藤原辰史
¥1,980
[版元サイトより引用] この本から、始まる 新しい世界史=「生きるための世界史」 あらゆる人が戦争と自分を結びつけ、歴史に出会い直すために。 アラブ、ポーランド、ドイツを専門とする三人の対話から はじめて浮かび上がる「パレスチナ問題」。 世界史は書き直されなければならない。 岡「今、必要としているのは、近代500年の歴史を通して形成された『歴史の地脈』によって、この現代世界を理解するための『グローバル・ヒストリー』です」 小山「西洋史研究者の自分はなぜ、ヨーロッパの問題であるパレスチナの問題を、研究領域の外にあるかのように感じてしまっていたのか」 藤原「力を振るってきた側ではなく、力を振るわれてきた側の目線から書かれた世界史が存在しなかったことが、強国の横暴を拡大させたひとつの要因であるならば、現状に対する人文学者の責任もとても重いのです」 目次 はじめに(岡真理) Ⅰ 私たちの問題としてのパレスチナ問題 岡真理「ヨーロッパ問題としてのパレスチナ問題――ガザのジェノサイドと近代五百年の植民地主義」 「ユダヤ人のパレスチナ追放による離散」は史実にない/ジェノサイドが終わるだけでは不十分/ハマスの攻撃は脱植民地化を求める抵抗/イスラエル政府の発表をうのみにしてはいけない/ジェノサイドはいかなるシステムによって可能になったのか/人文学=ヒューマニティーズから考える/ガザを見たとき、日本は自国の植民地主義を想起できているか/壁一枚を隔て、安楽な生活を享受する者/「人種」はヨーロッパ植民地主義が「発明」したもの/シオニズム運動――反セム主義に対する反応/国家維持のためにホロコーストの記憶を利用する/近代学問に内包されるレイシズム 藤原辰史「ドイツ現代史研究の取り返しのつかない過ち――パレスチナ問題はなぜ軽視されてきたか」 ナチズム研究者はナチズムと向き合いきれていない/ドイツとイスラエルをつなぐ「賠償」 /ふたつの歴史家論争/誰のための「記憶文化」か/ドイツは過去を克服した優等生なのか?/「アウシュヴィッツは唯一無二の悪だ」/奴隷制は終わっていない/経済の問題、労働の問題としてのナチズム Ⅱ 小さなひとりの歴史から考える 小山哲「ある書店店主の話――ウクライナとパレスチナの歴史をつなぐもの」 ふたつの戦争のつながり/長い尺度で問題を捉える/ポーランド書店 E. ノイシュタイン/ウクライナ-ポーランド-イスラエルを結ぶ生涯/イスラエルをリードした東ヨーロッパ出身者/「国家なき民族」の国歌/シオニズム運動はドレフュス事件より前にはじまっていた/民族運動の母体となった地域/移住して国家を建設するという発想/日本も「外部」ではない/「敵は制度、味方はすべての人間」 藤原辰史「食と農を通じた暴力――ドイツ、ロシア、そしてイスラエルを事例に」 私たちの食卓の延長にある暴力/投機マネーがもたらす飢餓/プーチンの農業政策は外交の武器/ウクライナの穀物を狙う米中/国際穀物都市オデーサ/飢餓計画を主導したヘルベルト・バッケ/ホロコーストの影に隠れる「入植と飢餓」/飢えてはならない人と、飢えてもいい人/イスラエルの食と水を通じた暴力/飢餓とは「低関心」による暴力 Ⅲ 鼎談 『本当の意味での世界史』を学ぶために 今の世界史は地域史の寄せ集め/「西」とはなんなのか?/ナチズムは近代西洋的価値観の結晶/「食を通じたイスラエルの暴力」に目が向かなかった反省/私たちの生活が奴隷制に支えられている/日本史、西洋史、東洋史という区分は帝国時代のもの/西洋史でパレスチナ研究をしたっていいはずなのに/ポーランドのマダガスカル計画/民族の悲哀を背負ったポーランドは、大国主義でもあった/イスラエル問題ではなく「パレスチナ問題」/イスラエルの暴力の起源は東欧に?/今のイスラエルのやり方は異常/押してはいけないボタン/核の時代の世界史/「反ユダヤ主義」という訳の誤り おわりに(小山哲) 本書成立の経緯(藤原辰史) [書籍情報] サイズ:128mm×188mm 製本:並製 ページ数:224ページ
-

中学生から知りたいウクライナのこと|小山哲 藤原辰史
¥1,760
[版元サイトより引用] 生きることの歴史、生きのびるための道。 黒土地帯、第二次ポーランド分割、コサック…地理や世界史の教科書にも載っているこうした言葉に血を通わせる。 「ウクライナを知る」第一歩はここからはじまる。 二人の歴史学者が意を決しておこなった講義・対談を完全再現。緊急発刊! MSLive! BOOKSシリーズ 「小国を見過ごすことのない」歴史の学び方を、今こそ! ・ロシアが絶対に許されない理由…? ・西側諸国、日本が犯してきた罪…? ・「プーチンが悪い」という個人還元主義では、負の連鎖は止まらない…? イベント参加者の声 ・歴史を知ることで、ニュースの解像度が上がり、そこに暮らす人びとの顔が見えてくるような感覚をおぼえました。 ・軍事評論家や国際政治学者の解説ではなく、こういう話が聞きたかったです。 ・「国」と「人」をいっしょくたにせず、どのように平和を築いていくのか。自分の姿勢を問い直す貴重な機会でした。 MSLive! BOOKSとは? ミシマ社が2020年5月にスタートしたオンラインイベント、「MSLive!」。 「MSLive! BOOKS」は、オンラインイベントのライブ感をそのまま詰め込んだ書籍シリーズです。イベントに参加くださった方々から、イベントの内容を活字化したものを販売してほしいというリクエストをたくさんいただき、実現することになりました。 目次 はじめに Ⅰ ウクライナの人びとに連帯する声明(自由と平和のための京大有志の会) Ⅱ ウクライナ侵攻について(藤原辰史) Ⅲ 講義 歴史学者と学ぶウクライナのこと 地域としてのウクライナの歴史(小山哲) 小国を見過ごすことのない歴史の学び方(藤原辰史) Ⅳ 対談 歴史学者と学ぶウクライナのこと(小山哲・藤原辰史) Ⅴ 中学生から知りたいウクライナのこと 今こそ構造的暴力を考える(藤原辰史) ウクライナの歴史をもっと知るための読書案内(小山哲) おわりに [書籍情報] サイズ:128mm×188mm 製本:並製 ページ数:208ページ
-

今の戦争がなんとなくわかる本|犬川わか
¥1,320
[版元サイトより引用] 2022年からのウクライナーロシア戦争と、2023年からのパレスチナーイスラエル問題について、イラストを使って解説しています。 また、イスラエル問題と切っても切り離せないユダヤ人問題についても解説。 まずは問題の概要をザックリと知りたい方 文字ばかりの本は読んでて疲れる、どこまで読んだか分からなくなる、という方 などにおすすめです。 内容は有識者の皆さまに監修いただいております。 [書籍情報] サイズ:210mm×148mm ページ数:68ページ
-

Decolonize Futures Vol. 1『反人種差別、フェミニズム、脱植民地化 | Anti-Racism, Feminism, and Decolonization』
¥1,650
[版元サイトより引用] 「家父長制、白人至上主義や人種差別。社会に存在する不平等や格差の原因は、植民地主義にあるのかもしれない。」 物理的な植民地支配が多くの地域で終わったにも関わらず、欧米諸国が行った経済的搾取や文化的な支配を通じて、暴力的な構造は今も私たちの生活に根付いています。 植民地主義の世界観では、欧米の文化が世界の中心であり、「シスヘテロ男性、白人(日本では人種的マジョリティである日本人)が最も人間らしい存在と見なされるヒエラルキーが生まれます。そして「女性/性的マイノリティ/有色人種の人々/非西洋の人々など」はヒエラルキーの下に位置付けられ、搾取され続けてきました。 Vol.1は、こうした現状に警鐘を鳴らし、フェミニズム、反人種差別がいかに脱植民地化と繋がるかを考える一冊です。 本号ではニューヨーク市立大学リーマン校のラローズ・T・パリス教授を招き、複数の社会課題が植民地主義と交差する様子に焦点を当てたレクチャーを行い、その講演を記事化しました。本文では、レクチャーや参加者との対話を可視化し、今の日本社会や言論空間において「脱植民地化」に関心を抱いた参加者と、ラローズ・T・パリス教授の対話の記録も紹介しています。 Patriarchy, white supremacy, and racism. Colonialism is lying beneath the inequalities in the world. Even though colonialism has ended in the form of physical occupation in many regions, a violent colonial system persisted through economic exploitation and cultural domination by Western nations and infiltrates our everyday lives. The colonial worldview is centered around Western culture and a hierarchy that assumes “White, (in Japan, Japanese) cis-hetero men” as most human while treating “women, LGBTQ+ people, people of color, non-Western indigenous people, etc” as inferior who deserve exploitation. Vol. 1 alerts to such reality and walks readers through how feminism, Anti-Racism, and Decolonization connect to each other. To think about how social issues intersect with the history of colonialism, we hosted a lecture with Dr. LaRose T. Parris, Associate Professor at CUNY, Lehman College. This issue is an archive of a dialogue between Professor Parris and the participants drawn to the topic of “decolonization” while living in contemporary Japanese society and discursive space. [書籍情報] 編:酒井功雄、saki・sohee サイズ:128mm×182mm ページ数:88ページ 言語:日本語と英語
-

Decolonize Futures Vol. 2『脱植民地化と環境危機 | Decolonization and the Environmental Crisis』
¥1,650
[版元サイトより引用] 2023年は、観測史上最も暑い年でした。気候変動によって台風や豪雨の被害が年々悪化している状況が、もはや当たり前のように感じてしまいます。環境の危機は、気候変動だけではありません。地球上の様々な生物種が、類を見ない速さで絶滅している「第6の大量絶滅」に入ったと言われています。 環境破壊や気候変動が悪化してきた歴史の背景には、環境破壊を肯定し推し進めてきた経済や政治、そして文化があります。植民地主義を通じて、植民地の人々や自然を搾取可能な「モノ」とみなし、土地を征服し切り開いてきたことが歴史的な環境破壊へと繋がっていきました。 Decolonize Futures Vol. 2「脱植民地化と環境危機」は、環境危機の根底にある植民地主義を批判し、オルタナティブな未来の可能性を研究する方々とのインタビューを収録した一冊となっています。 立教大学特任准教授の中野佳裕さんと、オーフス大学助教授の本田江伊子さんを招き、脱植民地化運動が様々な変化を遂げながら展開されてきた歴史、脱成長から考えるオルタナティブな未来の可能性、歴史をイデオロギー化せずに複数形の語りをすることの重要性といったトピックについて深掘ります。 2023 was the hottest year on record. It is no longer surprising to see the worsening situation of climate change. The environmental crisis extends beyond climate change. Human activities have caused the extinction of many species with an unprecedented speed, which is now called “sixth mass extinction.” Behind the history of the environmental crisis, there are culture, politics, and economy that have justified and progressed the environmental destruction. Through colonialism, people and the nature in the colonized countries and regions are turned into an exploitable “thing” or “resource,” and such discourse justified the historical destruction of the ecosystem worldwide. In Decolonize Futures Vol. 2 “Decolonization and the Environmental Crisis,” we organized interviews with scholars who criticize the colonialism lying beneath the environmental crisis and explore the possibility of alternative futures. With Yoshihiro Nakano (Rikkyo University) and Eiko Honda (Aarhus University), we will deep dive into the topics including the history of the decolonization movements, the alternative futures through degrowth perspective, and the importance of pluralizing the narratives of history. [書籍情報] 編:酒井功雄、saki・sohee サイズ:128mm×182mm ページ数:96ページ
-

Decolonize Futures Vol. 3『アイヌと脱/植民地化 | Ainu and De/colonization』
¥1,650
[版元サイトより引用] 今日の日本社会では、アイヌの人びとや文化を、SDGs推進やダイバーシティ・環境問題への取り組みの中で記号化・商品化し、市場において消費する植民地主義的構造が存在しています。 消費はマーケットの中のみならず、アイヌ文化や伝統を学術的や知的に考え論じる際にも、歴史的な差別や植民地主義による貧困、そしてその中でアイヌの人びとの身体が傷つけられ命が失われた事実を見過ごし、思想としてアイヌを消費してしまうことにも及びます。 また、植民地主義について考える際に、殖民者/被植民者、当事者/非当事者、加害者/被害者といった二元論的なフレームワークで語ることにより、その二元論から抜け落ちてしまう人びとの生や複雑な現実が不可視化されてしまいます。 「アイヌと脱/植民地化」と題したVol. 3では、北海道大学 アイヌ・先住民研究センター准教授で自身もアイヌの出自を持つ人類学者の石原真衣さんとともに、どのようにして記号化や消費に抗い、二元論的な構造に当てはまらない現実における脱植民地化を考えうるか、ということについて思考していきます。 In contemporary Japanese society, there is a colonial structure that commodifies and consumes Ainu people and culture within the frameworks of promoting SDGs, diversity, and addressing environmental issues. This consumption extends beyond the market to academic and intellectual discourse. Treating Ainu people as mere academic topics and ideas leads to overlooking the history of racism and poverty resulting from colonialism, and the suffering and deaths of many Ainu people. Furthermore, when discussing the Ainu people and colonial structures, understanding the reality in binary terms such as insider/outsider, perpetrator/victim, colonizer/colonized can render invisible the voices and existence of those who do not fit into these dichotomies. In this issue, we interviewed mai ishihara, an anthropologist at the Center for Ainu and Indigenous Studies at Hokkaido University and herself of Ainu descent, on how to resist tokenization/encoding and consumption and think about decolonization regarding the reality that does not fit into the dichotomies. [書籍情報] 編:酒井功雄、saki・sohee サイズ:128mm×182mm ページ数:96ページ
-

海をあげる|上間陽子
¥1,760
[版元サイトより引用] 「海が赤くにごった日から、私は言葉を失った」 おびやかされる、沖縄での美しく優しい生活。幼い娘のかたわらで、自らの声を聞き取るようにその日々を、強く、静かに描いた衝撃作。 ―――ねえ、風花。海のなかの王妃や姫君が、あの海にいる魚やカメを、どこか遠くに連れ出してくれたらいいのにね。赤くにごったあの海を、もう一度青の王国にしてくれたらいいのにね。でもね、風花。大人たちはみんな知っている。護岸に囲まれたあの海で、魚やサンゴはゆっくり死に絶えていくしかないことを。卵を孕んだウミガメが、擁壁に阻まれて砂浜にたどりつけずに海のなかを漂うようになることを。私たちがなんど祈っても、どこからも王妃や姫君が現れてくれなかったことを。だから私たちはひととおり泣いたら、手にしているものはほんのわずかだと思い知らされるあの海に、何度もひとりで立たなくてはならないことを。そこには同じような思いのひとが今日もいて、もしかしたらそれはやっぱり、地上の王国であるのかもしれないことを。だから、風花。風花もいつか、王国を探して遠くに行くよ。海の向こう、空の彼方、風花の王国がどこかにあるよ。光る海から来た輝くあなた、どこかでだれかが王妃の到着を待っているよ。(「アリエルの王国」より) 最後に知るタイトルの意味――その時、あなたは何を想うか。 目次 美味しいごはん ふたりの花泥棒 きれいな水 ひとりで生きる 波の音やら海の音 優しいひと 三月の子ども 私の花 何も響かない 空を駆ける アリエルの王国 海をあげる 調査記録 [書籍情報] サイズ:135mm×192mm ページ数:256ページ
-

裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち|上間陽子
¥968
[版元サイトより引用] 沖縄に戻った著者は、風俗業界で働く女性たちの調査をはじめる。ひとり暴力から逃げて、自分の居場所をつくっていく──彼女たちの語った話は著者の手で書き起こされ、目の前で読み上げられ、自己の物語として了解されていく。沖縄の話であり世界の話でもある、比類ない調査の記録である。 それは、「かわいそう」でも、「たくましい」でもない。この本に登場する女性たちは、それぞれの人生のなかの、わずかな、どうしようもない選択肢のなかから、必死で最善を選んでいる。それは私たち他人にとっては、不利な道を自分で選んでいるようにしか見えないかもしれない。上間陽子は診断しない。ただ話を聞く。今度は、私たちが上間陽子の話を聞く番だ。この街の、この国の夜は、こんなに暗い。 ――岸政彦(社会学者) 目次 まえがき――沖縄に帰る キャバ嬢になること 記念写真 カバンにドレスをつめこんで 病院の待合室で あたらしい柔軟剤 あたらしい家族 さがさないよ さようなら 調査記録 あとがき 十年後 [書籍情報] カバー写真:上原沙也加(『眠る木』より) カバーデザイン:鈴木成一デザイン室 サイズ:105mm×148mm ページ数:320ページ
-

ヤンキーと地元 解体屋、風俗経営者、ヤミ業者になった沖縄の若者たち|打越正行
¥990
[版元サイトより引用] 路地裏で、基地のネオンの道の片隅で、暗いコンビニの駐車場で、 バイクを止めて、彼らの言葉を拾う。 それは暴力以前にあったお話、掟を生きる前の傷みの話でもある。 掟がなぜ作られたのか、掟の外部はあるのか、 夜の街で拾われた言葉から考えたい。 ――上間陽子(教育学者) バイクのうなり、工事現場の音、キャバクラの笑い、深夜のコンビニ前のささやき。 本書を満たす音をどう聞き取るのが「正しい」のかは、まだ決まっていない。 ――千葉雅也(哲学者) 暴走族のパシリから始まった沖縄のフィールドワーク、10年超の記録。 解説 岸政彦 生まれ故郷が嫌いだと吐き捨てるように言った、一人の若者。その出会いを原点に、沖縄の若者たちをめぐる調査は始まった。暴走族のパシリとなり、建設現場で一緒に働き、キャバクラに行く。建設業や性風俗業、ヤミ仕事で働く若者たちの話を聞き、ときに聞いてもらう。彼らとつき合う10年超の調査から、苛酷な社会の姿が見えてくる──。補論を付した、増補文庫版。 「沖縄で出会ったヤンキーの拓哉は、「仕事ないし、沖縄嫌い、人も嫌い」と、吐き捨てるように言った。沖縄の若者が生まれ故郷を嫌いだとはっきり言うのを初めて聞いたので、私は驚いた。彼が嫌いな沖縄とはなんなのか。そもそも、彼はどんな仕事をし、どんな毎日を過ごしているのか。そうしたことを理解したいと私は思った。10年以上にわたる沖縄での調査の原点は、そこにあった。」(「はじめに」より) 目次 はじめに 第一章 暴走族少年らとの出会い 1 広島から沖縄へ 2 拓哉との出会い 3 警官とやり合う 第二章 地元の建設会社 1 裕太たちとの出会い 2 沖組という建設会社 3 沖組での仕事 4 週末の過ごし方 5 沖組を辞めていった若者たち 6 沖組という場所と、しーじゃとうっとぅ 第三章 性風俗店を経営する 1 セクキャバ「ルアン」と真奈 2 「何してでも、自分で稼げよ」 ―― 洋介の生活史 3 風俗業の世界へ 4 「足元を見る」ということ 5 風俗経営をぬける 6 性風俗店の経営と地元つながり 第四章 地元を見切る 1 地元を見切って内地へ ―― 勝也の生活史 2 鳶になる 3 和香との結婚、そして別れ 4 キャバクラ通い 5 地元のしーじゃとうっとぅ 6 キセツとヤミ仕事 7 鳶を辞め、内地へ 第五章 アジトの仲間、そして家族 1 家出からアジトへ ―― 良夫の生活史 2 「自分、親いないんっすよ」 ―― 良哉の生活史 3 夜から昼へ ―― サキとエミの生活史 おわりに あとがき 補論 パシリとしての生きざまに学ぶ ―― その後の『ヤンキーと地元』 1 パシリとして生きる 2 パシリとしての参与観察 3 フィールドへ 解説 打越正行という希望 岸政彦 [書籍情報] サイズ:105mm×148mm ページ数:368ページ
-

ミャンマー、優しい市民はなぜ武器を手にしたのか|西方ちひろ
¥1,980
[版元サイトより引用] ミャンマーの軍事クーデター後の1年間、目の当たりにした民主化闘争を、市民の声を丁寧に掬い上げ、リアルタイムで綴った稀有な記録。 選挙で民主主義政党に大敗したミャンマー国軍は、2021年2月、軍事クーデターを起こし全ての国家権力を握った。民意で選ばれた議員たちは拘束され、ミャンマーの人々は数年前にようやく手にした民主主義と自由を奪われる。 市民は最初、徹底した非暴力で抵抗を示した。しかし軍はそんな市民たちを虐殺し始める――。 国際協力のためにヤンゴンに住んでいた著者は、ミャンマー市民の闘いぶりをSNSで発信した。自由と民主主義を取り戻そうと奮闘する人々のひたむきな想いを、一人でも多くの日本人に伝え、ミャンマー市民とともに立ち上がってくれる人を増やすために。 闘いはまだ終わらない。終章には軍に抵抗する民主派の武装組織の兵士たち、日本で働く人たちの言葉なども掲載。ミャンマー市民たちの今を伝えている。 金井真紀さん (文筆家・イラストレーター) 推薦! 「涙が出る。ミャンマーの人がかわいそうだからじゃない、あまりにも勇敢だから」 高野秀行さん (ノンフィクション作家) 推薦! 「ミャンマーウォッチャーの私が強烈にお勧めしたい、反軍・民主化闘争のベスト本」 本書より抜粋 ・リーダーなどいないのに、誰もが自発的に、足りないものを補っていく。警察や兵士につけいる隙を与えない、秩序ある完璧な抗議。 ・「お金はいらない。僕らがほしいのは人権だ」 ・「暴力で返さないで。僕らの闘いを、世界に見てもらおう」 ・「ぜんぜん怖くないよ」 死ぬかもしれなくても? 「うん、死ぬかもしれなくても」 ・「内戦」ではなく「革命」と、彼は言った。 ・「クーデター後はみんな、宗教や人種などの壁を取り払って、新しい国をつくるために団結しなければいけないと思うようになったんだ」 目次 第1章 クーデターの衝撃 第2章 虐殺 第3章 奪われてゆく自由 第4章 武装化する人々 第5章 罪なき子どもたちの未来 第6章 新型コロナの悪夢 第7章 非日常下の社会 第8章 CDM参加者の声を聞く 第9章 戦闘が始まる 第10章 じりじりと強化される監視 第11章 闘いは続く 終章 [書籍情報] サイズ:132mm×183mm ページ数:272ページ
-

「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし
¥1,760
[版元サイトより引用] K-POPなどをきっかけに韓国に興味をもち日韓関係の歴史を学び始めた学生たち。しかし、ネットや家族・友人の言葉になんだかモヤモヤ。それはなぜか、自問し、語りあい、モヤモヤの根源を探りつつまとめた日韓関係「超」入門書。 目次 第1章 わたしをとりまくモヤモヤ 日本って全然寛容で優しい親切な国じゃない?! 推しが「反日」かもしれない‥‥‥ 「韓国が好き」と言っただけなのに なにが本当かわからなくて コラム 韓国人留学生の戸惑い 座談会 日韓の問題って「重い」? 第2章 どうして日韓はもめているの? 韓国の芸能人はなんで「慰安婦」グッズをつけているの? コラム マリーモンドと「少女像」 なんで韓国は「軍艦島」の世界遺産登録に反対したの? どうして韓国の芸能人は8月15日に「反日」投稿するの? コラム インスタ映えスポット 景福宮 コラム なぜ竹島は韓国のものだって言うの? 座談会 「植民地支配はそれほど悪くなかった」って本当? 第3章 日韓関係から問い直すわたしたちの社会 なぜ韓国人は「令和投稿」に反応するの? コラム K-POPアーティストが着た「原爆Tシャツ」 韓国のアイドルはなぜ兵役に行かなければならないの? コラム 韓国映画の魅力 日本人だと思っていたのに韓国人だったの? コラム 戦後日本は平和国家? 座談会 歴史が問題になっているのは韓国との間だけじゃない? 第4章 「事実はわかったけれど……」,その先のモヤモヤ K-POP好きを批判されたけど,どう考えたらいいの? コラム 『82年生まれ,キム・ジヨン』 ただのK-POPファンが歴史を学びはじめたわけ 韓国人留学生が聞いた日本生まれの祖父の話 韓国人の友達ができたけれど… 座談会 どんなふうに歴史と向き合うのか [書籍情報] 編:一橋大学社会学部加藤圭木ゼミナール 監修:加藤圭木 サイズ:148mm×210mm ページ数:184ページ
-

ひろがる「日韓」のモヤモヤとわたしたち
¥1,980
[版元サイトより引用] 「モヤモヤの連鎖」とも言える読者の反響を生み出した『「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし』から2年。大学院生と会社員になった編者が、朝鮮半島の人々との関係と社会のあり方を変えていくために、わたしたちに何ができるか真摯に語り合う。 目次 第1章 ひろがる「日韓」のモヤモヤ 語られはじめた「日韓」のモヤモヤ 『「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし』と出会ったわたし コラム 「日韓」の歴史を無視してK-POPを聴くことはできる? 座談会 「日韓」のモヤモヤと向きあう当事者性と想像力(ゲスト:平井美津子さん) 座談会 『「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし』への現役大学生の声にこたえる 第2章 「日韓」のモヤモヤとわたしたちの社会 「なにが本当のことかわからない」のはどうしてなの? 歴史否定と「有害な男性性」 韓国のなかでは歴史についてどう考えられているの? 学び場紹介 Fight for Justiceって? 座談会 ゼミの後輩たちは『「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし』をどのように読んだのか 座談会 加害の歴史を教えること,学ぶこと(ゲスト:平井美津子さん) コラム 取り消された毎日新聞・大貫智子氏の署名記事 座談会 『「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし』の刊行はわたしたちにとってどんな経験だったのか? 第3章 モヤモヤからわたしたちが出会った朝鮮 在日朝鮮人と日本人のわたし 100年前の東京で起きたこと コラム 多摩川を歩いて考える朝鮮 コラム 大阪・生野と京都・ウトロを訪ねて 沖縄と日本軍「慰安婦」問題 学び場紹介 ラオンって? 座談会 ソウルで考える朝鮮,日本で学ぶ朝鮮 第4章 終わらないモヤモヤとその先 社会運動に関わるということ 「そんなことより」と言えてしまうこと 学び場紹介 キボタネって? 座談会 日本社会を地道に変えていくこと [書籍情報] 編:朝倉希実加、李相眞、牛木未来、沖田まい、熊野功英 監修:加藤圭木 サイズ:148mm×210mm ページ数:240ページ
-

韓国社会運動のダイナミズム 参加と連帯がつくる変革|三浦まり 金美珍
¥2,860
[版元サイトより引用] 80年代の民主化闘争から近年のMeToo運動まで、社会を変える活力と戦略性を備えた韓国の市民・社会運動。女性運動、労働組合、革新政治との協同など、歴史的背景と豊かな実践例を各分野の当事者・専門家らが報告。 目次 はじめに 序章 韓国社会運動の歴史的変遷と再生への課題 第1部 #MeToo運動に結晶化した女性たちのたたかい 1章 「別々に、また、ともに」たたかってきた韓国の女性運動 2章 韓国の#Metoo運動はどのように展開したか 3章 政治家による性暴力事件と共同対策委員会 第2部 移民国家化する韓国と「外国人労働者」 4章 韓国の移民政策とその歴史的前提 5章 外国人雇用許可制度の評価と展望 6章 人権と労働権が保障される労働者受け入れ制度のために 第3部 住民参加に根ざした〈協治〉の試み 7章 社会を変えた韓国のダイナミズム――対立から参加型ガバナンスへ 8章 ソウル市革新10年からみる市民イニシアチブ 9章 市民運動の連帯とソーシャル・イノベーション 第4部 コロナ禍とエッセンシャル・ワーカーの権利 10章 コロナ禍における排除に対抗してきたエッセンシャル・ワーカーの運動 11章 なぜソウル市城東区はエッセンシャル・ワーカー条例を制定したのか 12章 運輸分野におけるエッセンシャル・ワーカーの実態と労働組合 13章 コロナ禍が照らし出す介護労働の公共性 第5部 活発化するベーシックインカム論争 14章 なぜ韓国ではベーシックインカム論争が盛り上がるのか 15章 韓国でベーシックインカム導入が現実的な選択肢である理由 16章 ベーシックインカムは福祉国家の発展をもたらすのか 終章 日本への示唆として何を受け取るか [書籍情報] 編:三浦まり、金美珍 サイズ:130mm×190mm ページ数:304ページ
-

現代思想2025年12月号 特集=排外主義の時代
¥1,980
[版元サイトより引用] 排除に抗する社会のために 世界的な右傾化のなか、日本でも改めて深刻さが浮き彫りになる排外主義。その現われに向き合い、核心を捉え、そして抗うことはいかに可能か。本特集では日常に潜む差別から法・制度的課題、さらには国境を超えた移動のありようやアイデンティティの問題にも目を配りつつ、さまざまな側面から排外主義の構造と実態に迫る。 目次 特集*排外主義の時代 討議 序列化する社会に抗して――「歴史修正主義」と「反移民」を貫くものを問う / 倉橋耕平+髙谷幸 現実を問う 高まる外国人の「処分可能性(ディスポーザビリティ)」 / 鈴木江理子 非人間化と制度的排外主義――日本における移民の搾取と排除 / 巣内尚子 「外国人」を取り締まる眼差し――レイシャルプロファイリング訴訟が問いかけるもの / 宮下萌 ヘイトスケープの増殖と「川口のクルド人」の現在地 / 三浦尚子 政治の行方 右派ポピュリズムが問いかけるもの / 山崎望 トランプの壁と排外主義 / 川久保文紀 極右政党はなぜ支持され、社会に何をもたらすのか / 五十嵐彰 排外主義とメディア信頼 / 秦正樹 応答への途 「排外主義」をめぐる堂々巡り――ある大学教員の日常から / 小ヶ谷千穂 境界を奏でる――排外の回路と音楽の公共性 / 中條千晴 排外主義と外来種――あるいはザリガニとその死体をめぐる考察 / 渡邉悟史 歴史と構造 「籍」と「血」の観念――レイシズムの温床となるもの / 遠藤正敬 不可視の隣人――結婚移住女性たちの過去と現在からの教訓 / 李善姫 アイヌへのレイシズムに潜む「権利と文化二分論」――不可視の植民地主義と法学の責任 / 小坂田裕子 制度を開く 社会的再生産をめぐる日本社会の矛盾――移民女性の身体から見るリプロダクティブ・ジャスティス / 田中雅子 外国人の「総量規制」は破綻する――量的統制の幻想と倫理 / 宮井健志 排外主義に陥らない反ジェントリフィケーションは可能か / 山本薫子 連載●社会は生きている●第四〇回 社会の制御 3――社会の分化と加工 / 山下祐介 連載●家族と憲法●第六回 明治期の家族法と憲法――「家」と一夫多妻制の行方 / 木村草太 研究手帖 力と聖書と時間のはざま、あるいは周縁で / 安田真由子 [書籍情報] サイズ:144mm×221mm ページ数:230ページ
-

小名浜ピープルズ|小松理虔
¥2,530
[版元サイトより引用] ぼくらはみな、だれかの悲しみのよそ者だ。 それでもなお、 他者との間の線を手繰り寄せる。 「他者(矛盾)を自分の中に招き入れ住まわせて、儀礼抜きに、迂路を介さず、問い問われ、問い直し、倫理を探し求めている」 ― 柳 美里( 小説家) 「〈中途半端〉の一語に自分の靄(かすみ)が晴れ、見知らぬ人々の顔がくっきりと見えてくる」 ― 三宅 唱( 映画監督) 東日本大震災と原発事故から10年。魅力的な地元の人々と話し、綴った、災間を生きるすべての人へ捧ぐ渾身の初のエッセイ 東北にも関東にも、東北随一の漁業の町にも観光地にもなりきれない。東日本大震災と原発事故後、傷ついたまちで放射能に恐怖し、風評被害は受けたが直接的被害は少なかった、福島県いわき市小名浜。著者は、この地で生まれ育ち〈中途半端〉さに悶えながら地域活動をしてきた。当事者とは、復興とは、原発とは、ふるさととは――10年を経た「震災後」を、地元の人々はどう捉え暮らしてきたのか。魅力的な市井の人々の話を聞き、綴った、災害が絶えない世界に光を灯す、渾身の人物エッセイ。 目次 「震災10年」と名物女将が守るチーナン食堂/処理水放出と海辺のまちの生業/老舗温泉旅館に生まれた原子力災害考証館/楢葉ルーツの解体業者がつくる未完の映画館/若き作家と響き合う常磐炭鉱の念/「被災地」であり、「被災地」でなかった双葉高校で/復興工事の現場から手繰り寄せる線/「そこにいく」から始まることーアシスタントの〈イチエフ〉視察記/流転する記者と重ね合う〈ふるさと〉/博覧強記の先輩と見渡す複数ある世界/我が子と語り合う、10万年後のこと [書籍情報] サイズ:128mm×188mm 製本:並製 ページ数:256ページ
-

声の地層 災禍と痛みを語ること|瀬尾夏美
¥2,310
[版元サイトより引用] 伝える人と耳を澄ます人をつなぐ、語り継ぎの文学 震災、パンデミック、戦争、自然災害…。多くを失い身一つになっても、集えば人は語りだす。痛みの記憶を語る人と聞く人の間に生まれた「無名の私たち」の記録。絵画多数掲載。 目次 はじめに――語らいの場へようこそ 第1章 おばあさんと旅人と死んだ人 第2章 霧が出れば語れる 第3章 今日という日には 第4章 ぬるま湯から息つぎ 第5章 名のない花を呼ぶ 第6章 送りの岸にて 第7章 斧の手太郎 第8章 平らな石を抱く 第9章 やまのおおじゃくぬけ 第10章 特別な日 第11章 ハルくんと散歩 第12章 しまわれた戦争 第13章 ハコベラ同盟 第14章 あたらしい地面 第15章 九〇年のバトン 声と歩く――あとがきにかえて [書籍情報] サイズ:128mm×188mm 製本:並製 ページ数:288ページ