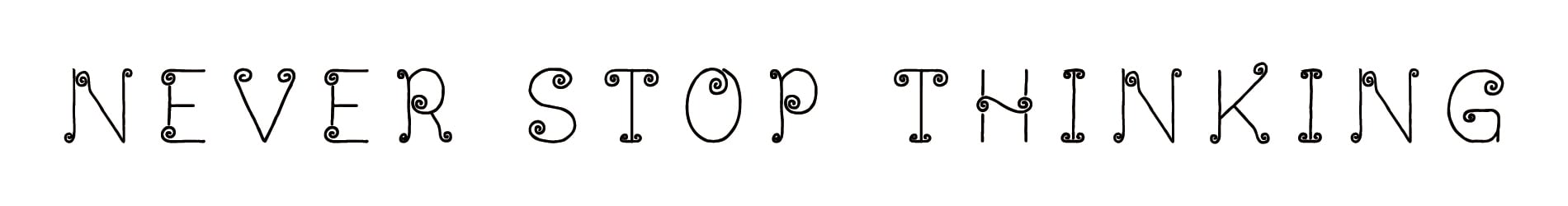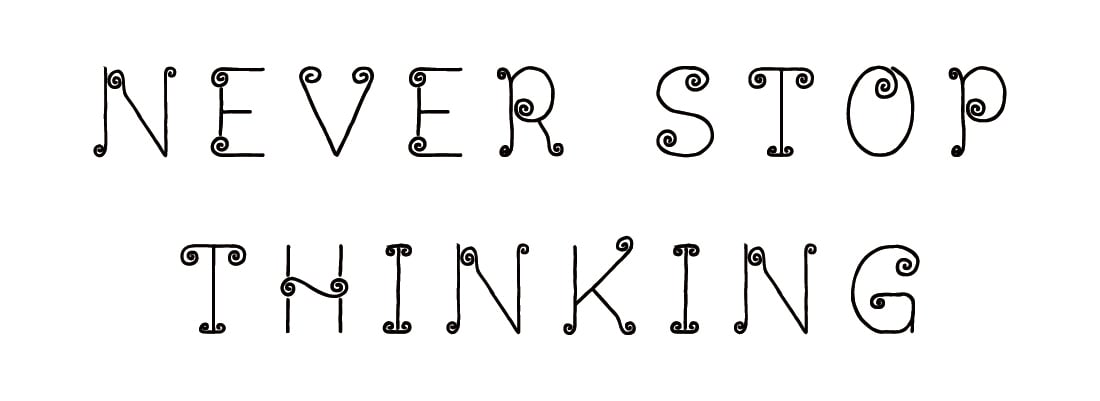-

誰のためのアクセシビリティ? 障害のある人の経験と文化から考える|田中みゆき
¥2,200
[版元サイトより引用] スロープや字幕を付ければ終わりではない。 アクセシビリティの先には、生々しい身体を持った人間がいる。 映画を観る、ゲームをする、アートを鑑賞する。 そのために、チケットを買う、座席を選ぶ、会場に行く。 多くの人が日常的にしていることを、マジョリティとは異なる身体を持つというだけで同じように楽しめない人たちがいる。 コンテンツを作るとき、情報を発信するとき、イベントを催すとき。 わたしたちは、自分と異なる身体と感覚を持つ人のニーズをどのくらい想像しているだろう? そもそも人が「体験する」とは、どういうことだろう? アクセシビリティについて考えることは、“当たり前”を問い直すこと。 『ルール?展』や『音で観るダンス』など、常識をくつがえすプロジェクトを生み出し、アクセシビリティを研究してきた著者が、障害のある人と対話・実験しながら書き上げた初のエッセイ! 障害のある人13人との対話・鑑賞ワークショップ・座談会の様子も記録。 「バリアフリー」や「インクルーシブ」からこぼれ落ちる声を聞き、AIなどのテクノロジーにも領域を広げて考える。 今の時代、どんな仕事、どんな表現をしている人も無関係ではいられない。 アクセシビリティの必要性と可能性、それを考えることの面白さも伝える著者ならではの人文エッセイ。 2024年度から改正障害者差別解消法の施行により、民間事業者も義務化となった「合理的配慮」。 何から始めよう?と考えている人も、はじめの一歩になる必読の本! “アクセシビリティは、社会のあらゆる場所が連携しながら、つくる人と使う人が一緒に更新していく、終わりのないプロセスなのだ。”(本文より) ※視覚障害、読字障害、上肢障害などの理由で紙の書籍を読むことが難しい方には、書籍をご購入されたご本人の私的利用に限り、テキストデータを提供しております。 書店やオンライン書店で本書をご購入いただいた方で、テキストデータをご所望の場合は、下記までお申し込みください。 メールアドレス:[email protected] 電話:03-3401-1042 [書籍情報] サイズ:128mm×188mm 製本:並製 ページ数:304ページ
-

サイボーグになる テクノロジーと障害、わたしたちの不完全さについて|キム・チョヨプ キム・ウォニョン
¥2,970
[版元サイトより引用] 世界が注目するSF作家と、俳優にして弁護士の作家。ともに障害当事者でもある二人が、私たちの身体性とテクノロジーについて縦横に語る。完全さに到達するための治療でなく、不完全さを抱えたままで、よりよく生きていくための技術とは? 韓国発・新しい社会と環境をデザインするための刺激的な対話。韓国出版文化賞受賞作。 目次 日本語版への序文………キム・チョヨプ、キム・ウォニョン はじめに………キム・ウォニョン Ⅰ われわれはサイボーグなのか 1章 サイボーグになる………キム・チョヨプ ダイヤモンド惑星のサイボーグの男 遠くて身近な障害者サイボーグ 向上ではなく変換する技術 2章 宇宙での車椅子のステータス………キム・ウォニョン 伴侶種車椅子 鏡の前の障害者サイボーグ 義足や車椅子は身体の一部だろうか 車椅子になって 3章 障害とテクノロジー、約束と現実のはざま………キム・チョヨプ 障害を克服するやさしい技術? 「わたしたちは障害を根絶します」 技術は障害の終焉をもたらすだろうか 4章 青テープ型サイボーグ………キム・ウォニョン 火星で生き残ったヒューマン 人間を超えた人間 ホーキングほど人間的でないなら 人間というアイデンティティーを問題視する存在 青テープのような存在たち Ⅱ ケアと修繕の想像力 5章 衝突するサイボーグ………キム・チョヨプ 見えない障害 サイボーグという烙印 サイボーグはロボットスーツを夢見るのか サイボーグの身体を維持すること 単一のサイボーグはない 6章 「障害とサイボーグ」のデザイン………キム・ウォニョン 骨工学の限界 マッコウクジラの骨と見えない補聴器 ファッションとディスクレション テクノロジー、障害、フェティシズム 「不気味の谷」を回避して 障害をデザインすること 7章 世界を再設計するサイボーグ………キム・チョヨプ 不具の科学技術を宣言する 知識生産者としての障害者 ユニバーサルデザイン、障害者中心のデザイン ストロー廃止は非障害者中心主義だろうか YouTubeとハッシュタグ、障害者運動の新しい波 仮想空間のアクセシビリティー 残された問い 8章 スーパーヒューマンの継ぎ目………キム・ウォニョン 障害を治す薬 治療を受けてキャプテン・アメリカになる? 滑らかさの誘惑 シームレスなデザインと継ぎ目労働 滑らかな世界に亀裂を入れる存在 ガタつきを甘んじて受け入れる力 Ⅲ 連立と歓待の未来論 9章 障害の未来を想像する………キム・チョヨプ わたしたちの異なる認知世界 あなたの宇宙船を設計してみてください 火星の人類学者たち サイボーグニュートラル 10章 つながって存在するサイボーグ………キム・ウォニョン 二本の脚で立てば依存しなくても済むのだろうか わたしを世話するロボット、わたしが世話するロボット 他人の顔を見なくてもいい生活 連立の存在論――「共にあること」を助ける技術 対談 キム・チョヨプ×キム・ウォニョン 一つのチームになる 生存以上の話 障害と科学技術の複雑な関係を考える 身体または存在を公表するきっかけ、オンラインとオフラインで 障害の経験の固有性 サイボーグという象徴に関して 人間と技術文明の切っても切れない関係 わたしたちの生が交差する瞬間 おわりに………キム・チョヨプ 謝辞 訳者あとがき 参考文献 [書籍情報] 著:キム・チョヨプ、キム・ウォニョン 訳:牧野美加 サイズ:128mm×188mm 製本:並製 ページ数:316ページ
-

きらめく拍手の音 手で話す人々とともに生きる|イギル・ボラ
¥1,980
[版元サイトより引用] 手話は言語だ。 [コーダ]=音の聞こえないろう者の両親のもとに生まれた、聞こえる子(Children of Deaf Adults)の話。 映画監督、作家であり、才気溢れる“ストーリー・テラー”、イギル・ボラ。 「コーダ」である著者が、ろう者と聴者、二つの世界を行き来しながら生きる葛藤とよろこびを、巧みな筆致で綴る瑞々しいエッセイ。 家族と対話し、世界中を旅して、「私は何者か」と模索してきた道のり。 あらすじ 著者は、「手話」を母語とし、幼い頃から両親の通訳をまかされ、早くから社会と接することで、成熟していった。 21歳で自らが「コーダ」と呼ばれる存在だと知った彼女は、同じコーダの仲間と知り合い、彼らの声を集めて、「コーダ」がどんな存在かを見つめなおす。 ある時、ろう者の父とともに、ろう文化の天国であるアメリカを訪れ、「デフ・ワールド・エキスポ」、ろう者に開かれたギャローデット大学で新たな文化と出会った。 帰国後、聞こえない両親、聞こえる自分と弟からなる自身の家族をみつめたドキュメンタリー映画の製作を決意。インタビューを重ね、彼らと自分の葛藤を映像の力で伝えることに挑んだ。 私は、手で話し、愛し、悲しむ人たちの世界が特別なんだと思ってきた。正確に言うと、自分の父や母が誰より美しいと思っていた。 口の言葉の代わりに手の言葉を使うことが、唇の代わりに顔の表情を微妙に動かして手語を使うことが美しいと。しかし、誰もそれを「美しい」とは言わなかった。世間の人たちはむしろそれを「障害」あるいは「欠陥」と呼んだ。 (一章「私はコーダです」より) 推薦コメント 読みながら胸が痛かった。けれどもこの痛みは、コーダが迎える未来を新しく切り開くものでもあった。 あなたとわたしの異なりからもたらされる喜び、そして、悲しみは、文化の出会いそのものだ。 ―― 齋藤陽道(写真家) ろう者の両親のもとで育った起伏に富んだ人生を表現することばの深さ、そして広がり。 この本は、ろう者とろう文化への格好の道案内として読むことができるだろう。 ボラさんのことばと思考は彼女のストーリーテリングにいくつもの輪郭を与え、多重露出のようなきらめきを与える。 ―― 斉藤道雄(ジャーナリスト/「解説」より) [書籍情報] 著:イギル・ボラ 訳:矢澤浩子 解説:斉藤道雄 装画・装幀:鈴木千佳子 サイズ:130mm×188mm 製本:並製 ページ数:288ページ
-

Harmony Letter 聴覚の多様性を探究するZINE
¥700
[版元サイト・インスタグラムより引用] 聴覚の多様性を探究するZINE『Harmony Letter』vol.2 コンテンツ ・「聞こえないママ」としての経験を描く、エッセイ漫画家 & イラストレーター うさささんへのインタビュー 漫画を描き始めた原動力/ 音が聞こえない世界/ デザインのキャリアが漫画にどう活きているか/ 聞こえない親と、聞こえる子ども。普段の会話の方法/ 自分らしい道を見つけるには ・コラム:聞こえのしくみ 難聴の種類を学ぶ 聞こえない世界で生きている方はもちろん、聞こえない世界に興味のある方にもぜひ手に取っていただきたい1冊です。 まえがきから抜粋 Harmony Letterは、生まれつき耳が聞こえず、両耳に人工内耳を装用している Yuuri と、言葉を手段に物事を伝えるコミュニケーションデザイン活動をしている Sakura が、心をこめて作っています。 ふたりの出会いは、2021 年、社会人 1 年目のときでした。偶然、近所に住んでいたふたり。「聴覚障害がある人の可能性を広げたい」という想いで活動していた Yuuriと、「中高生の未来の選択肢を増やすキャリア支援メールレター」をつくっていた Sakura の想いが重なり、意気投合しました。そして 2022 年 1 月、ZINE vol.1 を発行したことがはじまりです。vol.1 は今までに 30か所以上の聴覚特別支援学校、病院、難聴児の親の会などで配布してきました。 ふたりはしばらく、それぞれで活動を続けました。Yuuri はなんと、聴覚障害者と社会をつなぐプラットフォームを立ち上げることができました! Sakura は編集やコピーライティングの経験を積むうちに、想いを形にして伝えたい気持ちがふくらみ、Yuuri と再び ZINE をつくることに。 私たちと読者の方のあいだにハーモニーが生まれる場所になりますように。 [書籍情報] サイズ:143mm×211mm ページ数:8ページ 言語:日本語と英語
-

当事場をつくる ケアと表現が交わるところ|アサダワタル
¥2,200
[版元サイトより引用] 支援する/される関係を越えるため「当事者」から「当事場」へ。 当事者性をめぐる困難は「場」で分かち合う。 支援される側と支援する側の垣根を飛び越えるべく、音楽表現を軸にした多彩な活動を繰り広げてきたアーティスト。しかし、勤務先の障害福祉施設で重大なハラスメント事件が発覚。「豊かな日常」を支えるはずの福祉現場にはびこる権力・暴力に直面したとき、何ができるのか? 葛藤し続けた先に著者が見出したのは、〈場〉づくりの重要性だった。 社会の「当たり前」をゆさぶってきた著者が、自身もゆさぶられつつ綴った、福祉・アートについての体験エッセイ。 “私たちはその「当事者になり得なさ」を深く受け止めた先に、もっとふさわしいやり方で「当事者性」を感受し、熟考し、他者と対話をするための〈場〉を創る行動へと移すべきなのではないか。僕はその〈場〉を、「当事場」と名づける。”(本文より) 目次 序章 指で覆われる景色 背景コラム❶ 福祉現場における「支援」とは? 1章 「表現」というレンズで「障害」を考える 句点「。」の行方 この現場から、「考える」を耕す 「壁画」と「まなざし」 背景コラム❷ なぜ「支援」に「表現」が必要か 2章 支援者は「同志」になれるか?──高崎史嗣という「当事者」と出会って 生きてきた証は電波に乗って 粘る。いても、いなくても 「舟」に一緒に乗り込むこと 背景コラム❸ 「当事者(性)」にまつわる議論を追う 3章 「当事者性」が溶かされる場──復興公営住宅で編まれたラジオ あのとき あのまちの音楽から いまここへ あなたの「青い山脈」が、私の「青い山脈」になるとき 背景コラム❹ 続・「当事者(性)」にまつわる議論を追う 4章 どこにも向かわない「居場所」をどこまで続けられるか──再び品川の現場から 5章 性暴力とハラスメントについて考えた、「そばに居る者」としての記録 これまでのことを思い返す ちゃんと見ようとしなかったことについて書く 「個人」として引き受ける。「変化」のために 背景コラム❺ 「そばに居る者」を巡る「当事者性」 最終章「当事場」をつくる 「事件」と「福祉」はどうつながるか? 福祉における「非対称性」と「当事者性」の課題 人に着目した「当事者性」、場を主にする「当事場」 「強い当事者性」だけに囚われないために あとがき [書籍情報] サイズ:124mm×186mm 製本:並製 ページ数:264ページ
-

小山さんノート
¥2,640
[版元サイトより引用] 「小山さん」と呼ばれた、ホームレスの女性が遺したノート。 時間の許される限り、私は私自身でありたいーー2013年に亡くなるまで、公園で暮らしながら、膨大な文章を書きつづっていた小山さん。町を歩いて出会う物たち、喫茶でノートを広げ書く時間、そして、頭のなかの思考や空想。満足していたわけではなくても、小山さんは生きるためにここにいた。 80冊を超えるノートからの抜粋とともに、手書きのノートを8年かけて「文字起こし」したワークショップメンバーによるそれぞれのエッセイも収録。 小山さんのノートより 働きに行きたくない。仕事がかみあわない。もう誰にも言えない。私は私なりに精いっぱい生きた。(…)私にとって、大事なものは皆、無価値になって押し流されていく。(1991年11月7日) 雨がやんでいたのに、またふってくる。もどろうか。もどるまい。黄色のカサが一本、公園のごみ捨て場に置いてあった。ぬれずにすんだ。ありがとう。今日の光のようだ。(2001年3月18日) 駅近くに、百円ちょうど落ちていた。うれしい。内面で叫ぶ。八十円のコーヒーで二、三時間の夜の時間を保つことができる。ありがとう。イスにすわっていると、痛みがない。ノート、音楽と共にやりきれない淋しさを忘れている。(2001年5月7〜8日) 五月二十日、夜九時過ぎ、つかれを回復して夜の森にもどる。 にぎやかな音楽に包まれ、心ゆったりと軽い食事をする。タコ、つけもの、紅のカブ、ビスケット、サラミ少々つまみながら、にぎやかな踊りをながめ、今日も終わる。夜空輝く星を見つめ、新たな意識回復に、十時過ぎまで自由な時間に遊ぶ。合計五百十六円拾う。(2001年5月20日) ほっと一人ゆったりと歩く。のどがかわいた。水かコーヒーを飲みたい。こんな活気のない金曜の夜、三百円もち、何も買えない。人間の人生は生きてる方が不思議なくらいだ。(2001年6月22日) 一体、五十にもなって何をしているんだと、いい年をしてまだ本をもち、売れもしないもの書いて喫茶に通っているのか……と、怒り声が聞こえそうな時、私の体験の上、選んだ生き方だと、私の何ものかが怒る。(2001年6月14日) 私、今日フランスに行ってくるわ。夜の時間をゆっくり使いたいの……。美しい夕陽を見送り、顔が今日の夕陽のように赤く燃えている。(2001年6月27日) 2階カウンターの席にすわり、ノートと向かいあう。まるで飛行機に乗ったような空間。まだ3時過ぎだ。流れるメロディーに支えられ、フランスにいるような気持ちに意識を切り替える。(2002年2月21日) 一時間、何もかも忘れのびのびと終わるまで踊ることができた。明るいライトに照らされた足元に、一本のビンがあった。冷たい酒が二合ばかり入っている。大事にかかえ、夜、野菜と共に夜明けまでゆっくりと飲み、食べる。(2002年9月28日) 五時過ぎ、十八時間の飛行機に乗ったつもりで意識は日本を離れる。外出をやめ、強い風が吹き始めた天空、ゆらゆらゆれる大地、ビニールの音。 (2003年9月7〜9日) 目次 「はじめに――小山さんノートとワークショップ」登 久希子 「小山さんが生きようとしたこと」いちむらみさこ 小山さんノート 序 章 1991年1月5日〜2001年1月31日 第1章 2001年2月2日〜4月28日 第2章 2001年5月7日〜8月21日 第3章 2001年8月22日〜2002年1月30日 第4章 「不思議なノート」 2002年9月3日〜10月4日 第5章 2002年10月30日〜2003年3月16日 第6章 2003年7月3日〜2004年10月12日 小山さんノートワークショップエッセイ 「小山さんとノートを通じて出会い直す」吉田亜矢子 「決して自分を明け渡さない小山さん」さこうまさこ 「『ルーラ』と踊ること」花崎 攝 「小山さんの手書きの文字」藤本なほ子 「沈黙しているとみなされる者たちの世界」申 知瑛 [書籍情報] 編:小山さんノートワークショップ 装丁:鈴木千佳子 装画:いちむらみさこ サイズ:132mm×192mm 製本:並製 ページ数:288ページ
-

刑務所に回復共同体をつくる|毛利真弓
¥2,860
[版元サイトより引用] 「あなたについて教えてください」と聞かれても絶対最後まで話さないような、そんな記憶や体験について語ってもらう場をつくることが、私の仕事だった—— 対等性と自由が尊重された集団のなかで対話を行い、個々人が抱える問題や症状からの回復を目指す「回復共同体(TC)」。映画『プリズン・サークル』の舞台となった島根県の官民協働刑務所で、日本初となるTCの立ち上げに携わった心理士が、その実践を初めて綴る。 目次 序章 アミティの門を叩く——変化への入口 第I部 回復共同体と出会う 第1章 「援助職」という名の盾——少年鑑別所にて 第2章 専門家役割の模索——アミティとの出会いまで コラム1 グループが健康的な機能を発揮できないとき 第3章 回復共同体構築への準備——対話にならない会話 コラム2 TCの歴史 コラム3 「被害者等の心情等の聴取・伝達制度」に思うこと 第II部 回復共同体をともにつくる 第4章 罰を受ける場としての刑務所——トラウマティックな組織の住人たち コラム4 囚人化と犯罪者化 第5章 対話の文化を持ち込む——変化のための土壌づくり 第6章 話すことは放すこと——被害者から加害者へ、そして一人の「人」へ 第7章 対話の文化を根づかせる——回復共同体の成熟 コラム5 TCに関する当事者のネガティブな意見 第III部 回復共同体を支える 第8章 刑務官という役割——トラウマティックな組織の職員たち コラム6 組織のトラウマ コラム7 トラウマインフォームドケアの流行に思うこと 第9章 専門職もつらいよ——支援者集団の反応 第10章 援助職自身の成長と回復に向けて——手放すものとつかむもの 第IV部 回復共同体から離れて 第11章 つながりを社会へ——訓練生たちのその後 第12章 対話の場を広げる——治療法から尊重の文化へ あとがき 文献一覧 [書籍情報] サイズ:130mm×190mm ページ数:368ページ
-

集まる場所が必要だ 孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学|エリック・クリネンバーグ
¥2,640
[版元サイトより引用] ここでは、誰にも居場所がある。 シニアがゲームに熱狂する図書館、親どうしのつながりを育む学校、子どもがスポーツを楽しむ警察署… あらゆる人が受け入れられる「社会的インフラ」では何が行われ、何が生まれているのか。 1995年のシカゴ熱波で生死を分けた要因に社会的孤立があることを突き止めた著者。つながりを育み、私たちの暮らしと命を守るには何が必要なのか? 研究を通して見えてきたのは、当たり前にあるものとして見過ごされがちな場、「社会的インフラ」の絶大な影響力だったーー。 コロナ禍を経験した今こそ、私たちには集まる場所が必要だ。 目次 序章 社会的インフラが命を救う 第1章 図書館という宮殿 第2章 犯罪を減らすインフラ 第3章 学びを促すデザイン 第4章 健康なコミュニティ 第5章 違いを忘れられる場所 第6章 次の嵐が来る前に 終章 宮殿を守る [書籍情報] 著:エリック・クリネンバーグ 訳:藤原朝子 サイズ:136mm×195mm ページ数:352ページ
-

わたしがいる あなたがいる なんとかなる 「希望のまち」のつくりかた|奥田知志
¥1,870
[版元サイトより引用] 生きる意味のない“いのち”なんて、あってたまるもんか 困窮者支援のその先へ、誰もが「助けて」と言い合える居場所、「希望のまち」が誕生する 北九州市で生活困窮者を支援するNPO法人抱樸(ほうぼく)。1988年12月から路上で暮らすホームレスに弁当を配ることからスタートし、現在は居住や就業、子ども・家庭、障害福祉支援など29の事業を展開する。 著者は抱樸理事長で牧師の奥田知志氏。奥田氏と同法人の職員が出会った路上に生きる人や生きづらさに苦しむ人とのエピソード、新型コロナを経て現場で感じる社会の変化を綴る。単身世帯が増え、孤立が深まる中で自己責任論が蔓延、誰もが苦難に陥る可能性が高まっている。 こんな状況の中、2026年秋、三十数年の活動の集大成ともいえる「希望のまち」が完成する。この“まち” はどんな人も一人にしない“なんちゃって家族” になれる場所。分断と格差が広がり、偏見と差別が交じり合う社会に一石を投じる試みが始まるのだ。抱樸が理想とする「希望のまち」が生まれるまでの歩みと、未来への提言が満載。北九州の武内市長と小説家の町田そのこさんとの鼎談も収録。 [書籍情報] サイズ:128mm×188mm ページ数:288ページ
-

まちは言葉でできている|西本千尋
¥1,980
[版元サイトより引用] 都市計画の中で妊婦や子どもや障害者や女性や高齢者の存在が想定されていないこと、安全で快適な空間のためにホームレスの人々が排除されてきたこと、「公園まちづくり制度」の名の下に緑豊かな公園がなぜか消えていくこと、歴史ある町並みや昔ながらの銭湯を残すのがこんなにも難しいこと、「創造的復興」が被災者の生活再建に結びつかないこと―― 目の前にあるまちは、どのようにして今あるかたちになったのか。誰がそれに同意したのか。住民にまちを変えていく力はあるのか。「みんなのため」に進められる再開発の矛盾に目を凝らし、その暴力性に抗っていくために、専門家や行政の言葉ではなく、生活にねざした言葉でまちを語り直したい。 “すベて景色の前には「言葉」がある。わたしたちは「言葉」でまちをつくってきた。ある日突然、そこにブルドーザーが現れるのではない。必ず、その前に「言葉」がある。だからその「言葉」が変われば、ブルドーザーの現れ方も、立ち入り方も、去り方も変わり、まちのかたちも変わる。”(本文より) 「まちづくり」に関わるようになって約20年、現場で味わった絶望と反省を、各地で受け取った希望を、忘れないために記録する。ごくふつうの生活者たちに捧げる抵抗の随筆集。 “行政やデベロッパー主導の「まちづくり」に「わたし」は居ない。町にはひとりぼっちで居られる場所も、ひそかに涙を流す場所も必要だ。” ――森まゆみさん “暮らしに対して、ひとりひとりが誠実であるとはどういうことか。こういうことだったのだ。” ――武田砂鉄さん [書籍情報] サイズ:128mm×188mm ページ数:216ページ
-

ミュージックシティで暮らそう 音楽エコシステムと新たな都市政策|シェイン・シャピロシェイン・シャピロ
¥3,080
[版元サイトより引用] 音楽は都市のインフラだ! ライブハウスが減っていくのは「文化の問題」ではなく「都市政策の問題」かもしれない――。本書は、音楽を“社会のインフラ”ととらえ、まちづくりの戦略に音楽を取り入れる方法を説いた、新しい都市論です。 音楽や文化政策について都市と協働する英国のコンサルタント会社Sound Diplomacyの創業者が、ロンドン、アデレード、シドニー、オースティン、マディソン、ハンツヴィルなど、世界各都市と実際に取り組んできた政策やプロジェクトを紹介しながら、都市に音楽が根づくための条件をひもときます。 パンデミック以降、音楽業界が直面する困難を越えて、教育・観光・福祉・ジェンダー平等といった分野にも横断的に音楽が貢献できることを証明する、希望と戦略の書。 自治体職員、デベロッパー、都市プランナー、コミュニティデザイナー等々、町づくりに関わる人は全員必読です。 [書籍情報] 著:シェイン・シャピロシェイン・シャピロ 訳:エヴァンジェリノス紋子、若林恵 サイズ:130mm×182mm ページ数:344ページ
-

ケアとアートの教室
¥1,980
[版元サイトより引用] 藝大で福祉? 東京藝術大学学生と社会人がともに学んだ「アート×福祉」プロジェクトの記録。アートという光を当てると、見えないものが見えてくる 「死にたい人の相談にのる」という芸術活動 老人の方とつくる演劇で認知症を疑似体験 お葬式まで出すホームレス支援 セックスワーカーの法律相談 西成のおばちゃんと立ち上げるファッションブランド トリーチャーの当事者と考える「普通」とは何か 介護、障害、貧困、LGBTQ+、そしてアート。様々な分野で活躍する人々と、東京藝術大学 Diversity on the Arts プロジェクト(通称DOOR)の受講生がともに学び、考える。そこから見えてきたのは、福祉と芸術が「人間とは何かを問う」という点でつながっているということ。ケアとアートの境界を行く17項! 目次 はじめに 伊藤達矢 なぜ「アート× 福祉」? アートの特性が社会を変える 日比野克彦 講義編 「助けて」といえる社会へ ホームレス支援と「子ども・家族marugotoプロジェクト」 奥田知志 「風テラス」という試み セックスワーカーの法律相談 浦﨑寛泰 ダイバーシティと「表現未満、」 重度知的障害者と家族の自立 久保田翠 鬱から始まるアート 躁鬱研究家と「いのっちの電話」 坂口恭平 誰もが誰かのALLYになれる 多様な性のあり方とフェアな社会 松岡宗嗣 「アートなるもの」がアートを超える 服から始まるコミュニケーション 西尾美也 つながりがつくる希望 介護民俗学と「すまいるかるた」 六車由実 老いと演劇 認知症のひとと楽しむ「いまここ」 菅原直樹 罪を犯したひとたちとどう生きる? ドキュメンタリー制作から考える修復的司法 坂上香 実践編 福祉と建築が向き合う、答えなきもの 金野千恵×飯田大輔 普通って何だろう? 「見た目問題」を超えて 石田祐貴 日常というギフト 地域の「信頼」というセキュリティ ミノワホーム 誰かのミカタ地図 孤立したひとの居場所をつくる 香取CCC 他者について想像する力、変わろうとする力 田中一平 〈DOOR受講生鼎談〉 アートとは、福祉とは、多様性とは? [書籍情報] 著:飯田大輔、石田祐貴、浦崎寛泰、奥田知志、金野千恵、久保田翠、坂上香、坂口恭平、菅原直樹、西尾美也、日比野克彦、松岡宗嗣、六車由実 編著:東京藝術大学 Diversity on the Arts プロジェクト サイズ:130mm×183mm 製本:並製 ページ数:256ページ
-

私たちはなぜ犬を愛し、豚を食べ、牛を身にまとうのか カーニズムとはなにか|メラニー・ジョイ
¥2,860
[版元サイトより引用] 私達が当然のこととして受け入れているカーニズム(肉食主義)は、家畜動物に生まれてから死ぬまで、想像を絶する苦痛をもたらし、世界中のあらゆる場所で不正行為の原因ともなっている。また、この不可視化された信念体系は、私たちの考えを歪め、感覚を麻痺させている。カーニズムの成り立ちを、社会心理学的視点から分析し、畜産業に従事する人や一般人へのインタビューを交えた分析をもとにその仕組みを解き明かす、気鋭による画期の書。 [書籍情報] 著:メラニー・ジョイ 訳:玉木麻子 序文:ユヴァル・ノア・ハラリ サイズ:130mm×190mm ページ数:304ページ
-

とびこえる教室 フェミニズムと出会った僕が子どもたちと考えた「ふつう」|星野俊樹
¥1,870
[版元サイトより引用] 「ふつうって何だろう。」私はこれまで幾度となく、この言葉を心の中でつぶやいてきました。子どもの頃、スポーツが苦手で、女の子とおしゃべりをしたり、交換日記を書いたりするのが好きだった私。初恋の相手は男の子で、いわゆる「男子ノリ」にもなじめませんでした。そんな私に投げかけられたのは、「男の子ならふつうは〜」という言葉。大人になっても、「社会人の男ならふつうは〜」という声に息苦しさを感じます。 「ふつう」からこぼれ落ちる人たちの姿を見つめ、問いかけたいと思い、私は教師になりました。今では「ジェンダー」や「多様性」という言葉が広まったように見えますが、日本のジェンダーギャップは依然深刻です。学校でも、「異性愛が当たり前」「男らしさ・女らしさに従うべき」といった空気は根強く残っています。 本書では、「ふつう」とは何かを問い直しながら、子どもたちが自分らしく生きるために、教師として何ができるのかを考えていきます。 目次 はじめに 「ふつう」アレルギーの教師 私の人生と実践 第1章 男らしさに苦しんだ子ども時代 私はこんな家で育った 受験に失敗して入った私立小学校 先生に殴られないから「女子はずるい」 突如、暴力教師に変貌した塾の先生たち 父という暴君が支配する家 星野家を支える歯車の一つとして 「俺」という一人称が使えなかった僕の初恋 男社会のノリに過剰適応した中高時代 「男らしさ」を勘違いしていた男子高校生たち ジェンダー規範にとらわれない「虫愛づる姫君」を教えてくれた毛利先生 高校卒業時には自己責任論者に 第2章 学問と出会い、世界の見え方が変わる 大学に入って 学問と出会う はじめてのカムアウト 両親へのカムアウト 父に連れていかれたトランスジェンダー外来 大学で出会ったやさしい男たち—「クズィーズ」との出会い 「クズィーズ」のみんなと築いた友情 誰もが自分を語ることで楽になれるはず コラム「赦し」でもなく、「告発」でもなく 第3章 学校で壊れた私が自分の声を取り戻すまで 出版社を退職し教員をめざした理由 「こんなことをするために教師になったのか……」 休職中に感じた自分の「弱者性」への嫌悪 本を通じて服従の構造に気づく フェミニズムとの出会いで感情を言語化しはじめる 6ヶ月かけて書いた父への手紙 コラム 男らしさって悪いもの?—竹野内豊とドゥカティと僕 第4章 私の教育実践—「生と性の授業」 私を救ってくれたフェミニズム フェミニズムに目覚めた私が最初に取り組んだ「生と性の授業」 「女子力」という言葉をきっかけにジェンダーについて学ぶ 学びのタイミングは必然性を伴いやってくる 保護者に「生と性の授業」のねらいをどう説明したか 保護者の否定的な感想で実践から逃げたくなる 私に実践を決意させた壁の落書き セクシュアリティについて子どもたちにどう教えたか 子どもたちと「ふつう」について考える 卒業式の慣習を変えた子どもたち 「聞く非当事者」から「語る主体」へ変わった子どもたち 教育とは時間を必要とする営み 「生と性の授業」が子どもたちに教えてくれたこと 自分の人生の主導権を他人に渡すな 応えたのは誰のまなざしか—子どもの声を代償にして 承認されたい男、報われない教師 3つの形のトーンポリシング 「複合型トーンポリシング」を子どもたちにした私 ケアの不在と報われなさのゆくえ とびこえるダイアローグ① 毛利いずみ×星野俊樹 第5章 「自分らしさの教育」から一歩先へ 点から線を意識した実践へ 子どもも親も苦しい クラスに「男らしい文化」が蔓延して起きたこと 私がしてしまった暴力的な指導 「受容的なスタンス」の問題点 教室で再生産される性別役割分担 保護者からの反応 教師たちのジェンダーブラインドな反応 柔らかい声をエンパワーすること 「男らしさにとらわれた」男子たちの背景 暴力は構造から立ち現れる 子どもの文化に関心を持つこと 「だいじょうぶ?」で加害的な男子の心をほぐす コラム 秩序とは何か—「自由」と「抑圧」という二項対立をこえて 第6章 私の教育実践、私の物語 セクシュアリティを明かす葛藤 私には物語がいつも必要だった コラム 「性別にとらわれない」と「あえて性別にこだわる」の間で 第7章 語りが祈りになるとき ある男子中学生とのやりとり 語りを当事者に押しつけないために 傷つきと特権のはざまで、語り続けること 語れなかったことを語るために とびこえるダイアローグ② 前川直哉×星野俊樹 おわりに 母の刺繍、父の写真 謝辞 参考文献リスト [書籍情報] サイズ:127mm×188mm ページ数:252ページ
-

10代で知っておきたい「同意」の話 YES、NOを自分で決める12のヒント
¥1,815
[版元サイトより引用] 「NOじゃないならYES?」「相手の本当の答えを知るにはどうすればいい?」……同意は性の話に限らない。人間関係を築く上で欠かせない同意のイロハを親しみやすく、身近な例で紐解く。 [書籍情報] 著:ジャスティン・ハンコック イラスト:ヒューシャ・マクアリー 訳:芹澤恵、高里ひろ サイズ:128mm×188mm ページ数:160ページ
-

いばらの道の男の子たちへ ジェンダーレス時代の男の子育児論|太田啓子 田中俊之
¥1,540
[版元サイトより引用] 「プリキュアより仮面ライダーのほうが強い」と息子に言われたら、どうすればいい?――前著『これか らの男の子たちへ』が大反響だった弁護士の太田啓子さんと、「男性学」研究の第一人者・田中俊之さんが語り合う“令和版・ジェンダーレスな男子の子育て論”。雑誌『STORY』のWEB連載を再構成し、かつ書籍化にあたり、灘中高等学校の名物教師や、YouTubeの性教育コンテンツが話題のバービーさんなど、4名のキーパーソンを取材。 [書籍情報] サイズ:128mm×188mm ページ数:224ページ
-

母になる|久木田依子
¥1,500
[版元サイトより引用] このzineは、私の妊娠9ヶ月と出産、そして産後数ヶ月を記録したものです。 心と体と世界、すべてが大きく変化していく時期。そんなカオスの中で、思い立った時に描き下ろした言葉や写真を並べ、ばらばらだった点たちを一つの線で繋げてみました。私の体験が特に特別だと感じたからではなく、あくまでも一人のある体験として、でも「母親」という存在になっていくプロセスを祝福して、妊娠や出産、産後の日常を多くの人に共有したくて冊子としてまとめました。 ※ステッカーが一冊につき、一枚付いてきます。妊婦マークではないけど、お母さんになる人、お母さんたち、お母さんたちをサポートする意味で、色んなところに貼って下さい! [書籍情報] 著・デザイン:久木田依子 サイズ:148mm×210mm ページ数:36ページ [その他] zineとステッカーの他に、2025年6月3日に著者が記したあとがき(A4サイズ1枚)もお付けします。
-

ヘルシンキ 生活の練習|朴沙羅
¥990
[版元サイトより引用] フィンランドの子育てに、目からうろこ。 「母親は人間でいられるし、人間であるべきです」 二人の子どもと海を渡った社会学者による現地レポート。 「考え方が変わる」と大反響。待望の文庫化! 「これらのスキルはすべて、一歳から死ぬまで練習できることですよ」二人の子どもを連れ、新しい土地で生活を始めた社会学者の著者は、日本とのちがいに驚かされつつ、出会ったひとたちからたくさんのことを教わっていく。「フィンランドは理想郷でもないし、とんでもなくひどいところでもない」たんたんと、関西弁のユーモアを交えて描かれる、北欧のレポート。 「フィンランド(に限らず、北欧)は理想郷のように描かれるときがある。かと思うと、そんなことはないのだ、これがフィンランド(と北欧)の真実だ、と悪い情報を流す言説を見ることもある。 でもたぶん、それはどちらも正確ではない。フィンランドは理想郷でもないし、とんでもなくひどいところでもない。単に違うだけだ。その違いに驚くたびに、私は、自分たちが抱いている思い込みに気がつく。それに気がつくのが、今のところは楽しい。」 (「4 技術の問題――保育園での教育・その2」より) 目次 はじめに 1 未知の旅へ――ヘルシンキ到着 2 VIP待遇――非常事態宣言下の生活と保育園 コラム1 ヘルシンキ市の公共交通機関と子ども車両 3 畑の真ん中――保育園での教育・その1 4 技術の問題――保育園での教育・その2 5 母親をする――子育て支援と母性 コラム2 社会とクラブと習い事 6 「いい学校」――小学校の入学手続き 7 チャイコフスキーと博物館――日本とフィンランドの戦争認識 コラム3 マイナンバーと国家への信頼 8 ロシア人――移民・移住とフィンランド コラム4 小学校入学 おわりに 注 文庫版あとがき 解説 坂上香 [書籍情報] 著:朴沙羅 解説:坂上香 装丁・装画:寄藤文平+垣内晴(文平銀座) サイズ:105mm×148mm ページ数:320ページ