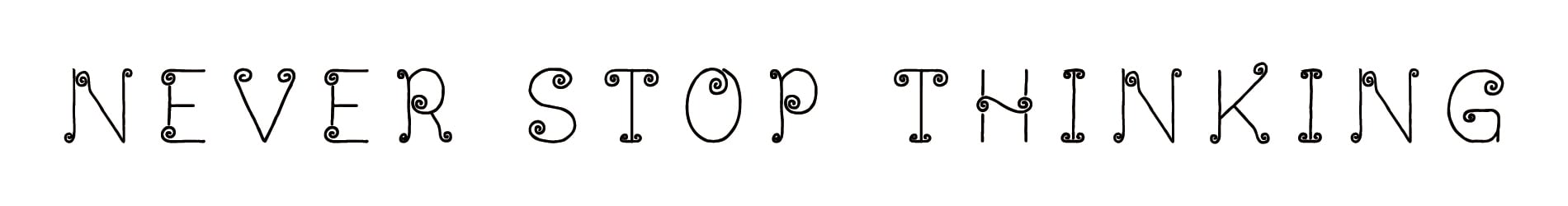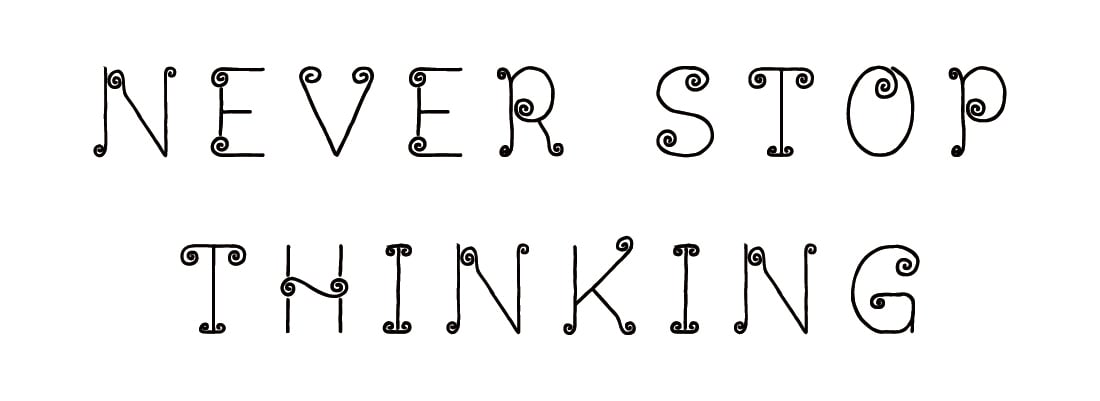-

ふつうの人が小説家として生活していくには|津村記久子
¥1,760
[版元資料より引用] 2005 年に太宰治賞の受賞作『君は永遠にそいつらより若い』でデビューした津村記久子さんは今年、デビュー20 周年を迎えます。 休むことなく、『ポトスライムの舟』、 『ディス・イズ・ザ・デイ』 『つまらない住宅地のすべての家』、 『水車小屋のネネ』 などの傑作を発表し続けた作家はどのように暮らし、どのように小説を書いてきたのか? 同世代の編集者が共通の趣味である音楽、サッカーの話をまじえながら、その秘密を根掘り葉掘り聞きました。「オープンソースだけで仕事をしてきた」と語る「ふつうの人」がなぜ、唯一無二の作家となったのかを解き明かす、元気が出て、なにかを書きたくなる、ロング・インタビュー。名言がたくさんです。 [書籍情報] 著:津村記久子 聞き手:島田潤一郎 サイズ:120mm×180mm ページ数:208ページ

-

季刊日記 創刊号
¥2,178
[版元サイトより引用] あなたは日記をつけたことがありますか? 夏休みの宿題として、友達との交換日記として、業務上の日報として、SNSの日々の投稿として――私たちは、生まれてから死ぬまでの間に、何度も日記に出会います。 日記は、まず日付ではじまります。あとは今日見たもの、感じたこと、考えたことなど、なんでも自由に書いていくことができます。最も自由な形式、といえるかもしれません。 あなたは日記を読んだことがありますか? 日記は、必ずしも自分ひとりのために書かれたものばかりではありません。最近では、商業出版される書籍はもちろん、個人でつくられるZINEやリトルプレスも含めて、日記の本がとても増えています。 SNSでは「見られる」ことが強く意識される一方、生成AIが出力した投稿も見分けがつかないようになりました。日々を生きる人間の「私」に近いことばへの関心が、これまで以上に高まっています。 私たちは、日記を書くこと/読むことの魅力を、さまざまな角度から深めていけるような雑誌をつくりたいと考え、ここに『季刊日記』を創刊することにしました。日本はもちろん、おそらく世界でも類を見ない、日記の専門誌です。 たっぷり日記を読める「25人の1週間」を定番企画として、毎号さまざまな特集を組んでいきます。創刊号の特集は「日記のたのしみ」「日記とホラー」です。 今日から日記がたのしくなる、これまでにない文芸誌の誕生です。 目次 25人の1週間 多様な執筆者による、同じ1週間の日記 安達茉莉子/伊藤亜和/猪瀬浩平/小沼理/北尾修一/こうの史代/古賀及子/こだま/桜林直子/図Yカニナ/武田砂鉄/ドミニク・チェン/鳥トマト/蓮沼執太/葉山莉子/ピエール瀧/東直子/浮/藤原辰史/堀合俊博/前田隆弘/牧野伊三夫/松浦弥太郎/柚木麻子/尹雄大 特集1:日記のたのしみ 対談:植本一子 × pha「すぐ手元から始める、表現のヒント」 インタビュー:福尾匠 × 荘子it「シットとシッポにきく」 エッセイ:金川晋吾/蟹の親子/ネルノダイスキ/品田遊 レビュー:me and you(竹中万季、野村由芽) 特集2:日記とホラー 対談:大森時生 × 山本浩貴(いぬのせなか座)「なぜホラーと日記がブームになったのか」 エッセイ:初見健一/柿内正午 レビュー:林健太郎 その他 座談会:株式会社インテージ × 日記屋 月日「日記をつけるプラットフォームを作りたい」 読者投稿 次号予告:「日記のくるしみ/日記と植物」 [書籍情報] 発行:日記屋 月日(tsukihi.jp) 書籍設計:明津設計(akitsusekkei.com) サイズ:145mm×210mm ページ数:352ページ

-

みんなもっと日記を書いて売ったらいいのに|小沼理
¥1,320
[版元サイトより引用] 半年間だけ出していた『月刊つくづく』の同名連載にくわえて、あらたに飯田エリカさん、僕のマリさん、星野文月さんとの日記にまつわる対談を収録。 社会が混迷を極めるなかで、個人が日記を書き、売る。その行為の先に何があるのか。わたしの個人的な問いかけに端を発する、小沼理さんの日記にまつわるエッセイ集。巷では日記ブームとも言われていますが、日記って何でしょう。その一端を掴んでいただけたら幸いです。(『つくづく』編集人・金井タオル) [書籍情報] サイズ:100mm×210mm ページ数:84ページ
-

彼女の最初のパレスチナ人|サイード・ティービー
¥2,860
[版元サイトより引用] パレスチナ移民たちの心情を描く傑作短篇集 力によって追放され、世界のどこにいようと「よそ者」として日常を引き裂かれ続けるパレスチナ人たちは、あなたのすぐ隣にもいるかもしれない。ーー安田菜津紀氏(Dialogue for People副代表/フォトジャーナリスト)推薦! 2022年アトウッド・ギブソン・ライターズ・トラスト・フィクション賞最終候補作 母国について教えた恋人が救済活動に目覚めていく姿に戸惑う医師 かつて暮らした国への小さな投稿によって追い詰められていく数学者 ルームメイトたちに溶け込むために架空の恋人をでっちあげる大学生 正規採用と引き換えに違法なミッションを引き受けてしまう司法修習生 妻と娘のために禁断の取引に手を伸ばしてしまうプログラマー…… 安住の地となるはずの国で心揺らぐパレスチナ移民たちの日々が、珠玉の9篇に。瀬戸際に追い詰められながら自らのアイデンティティを探る姿を多彩な筆致で綴る、カナダ発傑作短篇集。 [書籍情報] 著:サイード・ティービー 訳:大津祥子 サイズ:130mm×188mm ページ数:272ページ
-

隙間1|高妍
¥902
SOLD OUT
[版元サイトより引用] 「人の感情はどこから来て、どこへ向かうのだろう?」 台湾・台北に暮らす女子大生の楊洋(ヤンヤン)。心をすり減らしながらも懸命に介護を続けていた大切な祖母を亡くし、深い悲しみに沈む日々を過ごしていた。さらに、想いを寄せていた男性には別の恋人がいて、自分を愛してくれない……。すべてから逃げるように、楊洋(ヤンヤン)は交換留学生として、近くて遠い異国・沖縄へと旅立った。異国の地での生活は、祖母との思い出や恋の痛みを抱えたまま始まったが、沖縄の人々との交流やその地に刻まれた歴史に触れる中で、少しずつ“私”を取り戻していくーー。 「この残酷な現実に“さよなら”を告げて、私は行く。異国・日本へ。“はじめまして”を見つける旅へ」 好きな音楽を聴き、本を読み、映画を観て、恋愛をして、普通の大人になりたかった“私たち”の、青春の“怒り”と“記憶”。フリースタイル「THE BEST MANGA 2023 このマンガを読め!」第2位&宝島社「このマンガがすごい!2023」オトコ編・第9位ランクイン、『緑の歌 - 収集群風 -』で鮮烈なデビューを飾った高妍(ガオ イェン)が紡ぐ、台湾と日本、過去と未来、私とあなたの物語。超厚【250ページ】の第1巻。 [書籍情報] サイズ:128mm×182mm ページ数:250ページ
-

隙間2|高妍
¥946
[版元サイトより引用] 「琉球と台湾の歴史って、似てると思うんだ」 留学生として沖縄での暮らしを始めた、台湾人の楊洋(ヤンヤン)。沖縄で生きる人々、そして同じく留学生として日本にやってきた中国人の李謙(リーチェン)や台湾人のワンティンと関わる中で、彼女は自身と他者、母国と沖縄、それぞれのアイデンティティに向き合うことになる。一方、台湾では、楊洋(ヤンヤン)が想いを寄せる青年・Jが、国民投票に向けて活動を活発化させていた。異なる土地でそれぞれが抱える葛藤と希望は、やがて……。 「怒りも悲しみも、全部。行き場のない感情を乱暴に撒き散らしてでも、伝えたい想いがあった、あの頃」 ひまわり学生運動、表現の自由、同性間の婚姻の保障、国民投票。私たちが私たちであり続けるために、私は飛び出す。“怒り”と“愛”を抱きしめて。フリースタイル「THE BEST MANGA 2023 このマンガを読め!」第2位&宝島社「このマンガがすごい!2023」オトコ編・第9位ランクイン、『緑の歌 - 収集群風 -』で鮮烈なデビューを飾った高妍(ガオ・イェン)が“今”に放つ、新境地。超厚【282ページ】の第2巻。 [書籍情報] サイズ:128mm×182mm ページ数:282ページ
-

隙間3|高妍
¥880
[版元サイトより引用] 「あなたのことが、好き。知ってるでしょ、ねえ?」 台湾・台北に住む青年・Jへの届かぬ想いに心を痛める楊洋(ヤンヤン)。台湾にも沖縄にも居場所を見つけられない彼女は、亡き祖母との記憶を手繰り寄せながら、自らの未来を模索する。「私が、私であるために」ーー母国と似た風の中で、彼女は立ち上がる。台湾と沖縄に、絶望と希望に、私とあなたに、手を伸ばす……。 「二二八事件の犠牲者は台湾人だけじゃない。琉球人も確かにここにいたんだ」 歴史と文化を、そして植民地化された悲しみを共有している台湾と琉球。それぞれの歴史と人を見つめることで、楊洋(ヤンヤン)は台湾人としてのアイデンティティを確立していく……。フリースタイル「THE BEST MANGA 2023 このマンガを読め!」第2位&宝島社「このマンガがすごい!2023」オトコ編・第9位ランクイン、『緑の歌 - 収集群風 -』で鮮烈なデビューを飾った高妍(ガオ イェン)が贈る、あなたへの手紙。超厚【234ページ】の第3巻。 [書籍情報] サイズ:128mm×182mm ページ数:232ページ
-

隙間4|高妍
¥968
[版元サイトより引用] 「私たちにはまだ時間がある。一緒に沖縄のことを知ろうよ!」 祖母の死、そして報われぬ恋。すべてを振り切るように飛び込んだ留学生活も、終わりを迎えようとしていた。台湾に生まれ、台湾人として生きる楊洋(ヤンヤン)。残された時間の中で、彼女は沖縄の歴史と文化に心を寄せる。母国と縁深いこの地を知ること。それは、自身を見つめ直すことでもあると信じて。ーー“私”はもう、孤独じゃない。 「私たちも、台湾のことをもっと知りたいんだ!」 植民地化、二二八事件、ひまわり学生運動、表現の自由、沖縄戦……。葛藤の歴史を抱える台湾と沖縄を見つめ、自らを見つめ、未来を見つめる楊洋(ヤンヤン)の、そして、普通の希望が欲しかった“私たち”の、青い覚悟。台湾と日本、歴史と現在、社会と個人、私とあなた……名もなき隙間に光を見つける、私たちの物語、完結。 フリースタイル「THE BEST MANGA 2023 このマンガを読め!」第2位&宝島社「このマンガがすごい!2023」オトコ編・第9位ランクイン、『緑の歌 - 収集群風 -』で鮮烈なデビューを飾った高妍(ガオ イェン)が贈る、未来へのメッセージ。超厚【290ページ】、最終第4巻。 [書籍情報] サイズ:128mm×182mm ページ数:290ページ
-

YOKOKU Field Notes #01 台湾・編みなおされるルーツ
¥1,320
[版元サイトより引用] 日本・鹿児島でのフィールドリサーチに端を発しその流れを継ぐ〈YOKOKU Field Notes〉第1号となる本書では、外来文化に翻弄されてきた複雑な歴史を背負う台湾をフィールドに、人々が共に生きるための拠り所となる「ルーツ」を問いの切り口として、5つの事例を巡ります。 ・老朽化した台北の巨大団地街一体に根付き、受け継がれる福祉活動の現場〈南機場〉 ・花蓮の東海岸を舞台に、”魚育”から台湾の海洋食・漁業に光を当てる〈洄遊吧(FISH BAR)〉 ・教師, 親, 生徒という立場が流動する、原住民語のみの実験学校〈Tamorak 阿美語共學園〉 ・アミ族の規範と青年同士の協働のあわいで催される音楽フェスティバル〈阿米斯音樂節〉 ・バンド活動の傍ら農家として地元・旗山のバナナ産業に根ざす〈台青蕉樂團(Youth Banana)〉 これら台湾各地に点在する新たな営みの断片を捉え、変えられない本質としてのルーツに対峙し、自らの存在の意味と居場所を編み直そうとする人々の活動を手がかりに、ルーツの構築可能性について考えます。 目次 ◎ リサーチの概要 ◎ コラム:台北、市井の生活者より──台湾社会にふれる7つの主題 ◎本編:編みなおされるルーツ 事例1:南機場地区・忠勤里 都市の人生を養い継ぐ 事例2:洄遊吧(FISH BAR) 渦巻く海への感懐 事例3:Tamorak 阿美語共學園 言葉の焚き火を囲んで 事例4:阿米斯音樂節 境界を揺らす “民族” の複音 事例5:台青蕉樂團(Youth Banana) 故郷の根茎が紡ぐ詩 ◎ 編集後話 〈YOKOKU Field Notes〉について 〈YOKOKU FIeld Notes〉は、コクヨが目指す「自律協働社会」の兆しを個別の地域から探索するヨコク研究所のリサーチ活動とそのレポートです。 同じ時代を異なる環境条件で生きる人々の中に身を投じ、聞き取りや観察を含むフィールドワークを通じてその営みの断片にふれることで、既存のシステムや規範をかいくぐるオルタナティブな社会のあり方を探り、また問い直すことを目的としています。 [書籍情報] 発行:コクヨ株式会社 サイズ:182mm×257mm ページ数:120ページ
-

YOKOKU Field Notes #02 韓国・勝ち敗けのあわい
¥1,320
[版元サイトより引用] 「競争」の枠組みを超えて他者と交わるための、6つの活動のケース・スタディ ルーツの構築性をテーマに台湾各地に芽生える営みを紹介した01号に続き、本号のリサーチは、競争原理や能力主義が席巻する今日の韓国社会をフィールドにしています。その問いは、競争が枕詞になって久しい「教育」や「経済活動」の分野のみにとどまらず、「地域間格差」「遺伝情報としての種子の市場価値」「国家間の友敵関係」も射程に収めます。”勝ち/敗け”というフレームを脱して世界を作り変えようとする、韓国各地の6つの自律的・協働的な取り組みに注目します。 韓国各地に点在する新たな営みの断片を捉え、人々が不本意な他律的基準に巻き取られることなく、主体のままで他者に揉まれながら共存するための構えを考える一冊です。 ・〈Library tTsome〉京畿道 城南市 中院区 12~19歳の青少年に無料のサードプレイスを提供する私設公共図書館 ・〈ソウル鉛筆〉ソウル特別市 鍾路区 対話や読解、廃棄物を使った遊びから子どもの自律性を養う組織 ・〈南海尚州 同苦同楽協同組合〉慶尚南道 南海郡 尚州面 村を一単位として文化と経済の循環をめさす協同組合 ・〈穀物集〉忠清南道 公州市 鳳凰洞 在来穀物を介して持続可能な食文化を次世代に手渡すコレクテイブ ・〈1 Euro Project〉ソウル特別市 城東区 地域と商業の関係を問い直す小商いの複合施設 ・〈DMZ SPACE〉京畿道 波州市 郡内面 非武装地帯の森から新たな農林業と観光のあり方を提示する6次産業プロジェクト 目次 概要 ・リサーチを紐解くキーワード ・「勝ち敗けのあわい」を探る6つのケース・スタディ 本編 ・事例1:Library tTsome / ソウル鉛筆 京幾道、放課後のアジール ・事例2:南海尚州 同苦同楽協同組合 協同組合が育てる‘‘蓄積しない"村のエコシステム ・事例3:穀物集 蒔きなおされる種──「市場」と「保存」の畝のすきま ・事例4:1 Euro Project 廃ビルと商店からはじめる、健全なジェントリフィケーション ・事例5:DMZ SPACE 地図に依らない生──森、観光、DMZ コラム ・競争社会を越えて、世界に応答せよ!(鳥羽和久) ・韓国の葬儀と家族、その変化と不変の間(金セッピョル) ・なかったところに線を引くためのレッスン(斎藤真理子) 編集後話 〈YOKOKU Field Notes〉について 〈YOKOKU FIeld Notes〉は、コクヨが目指す「自律協働社会」の兆しを個別の地域から探索するヨコク研究所のリサーチ活動とそのレポートです。 同じ時代を異なる環境条件で生きる人々の中に身を投じ、聞き取りや観察を含むフィールドワークを通じてその営みの断片にふれることで、既存のシステムや規範をかいくぐるオルタナティブな社会のあり方を探り、また問い直すことを目的としています。 [書籍情報] 発行:コクヨ株式会社 サイズ:182mm×257mm ページ数:128ページ
-

YOKOKU Field Notes #03 インドネシア・集まり方の作法
¥1,320
[版元サイトより引用] 自律協働的な「集まり方」を巡る、4つの活動のケース・スタディ ルーツの構築性をテーマに台湾各地に芽生える営みを紹介した01号、韓国で”勝ち/敗け”の枠組みの外にある取り組みを探った02号に続き、本号では「集まり方」、すなわち個人同士が集い協働へと発展するプロセスを問い直すべく、インドネシア各地をフィールドに、4つの活動の背景と環境、当事者の姿勢を取材・レポートしています。 民族・言語・宗教・自然生態系に至るまで、多様な島々が一つの国家として成立するインドネシア。現代美術の分野を中心に、協働的な活動形態である「コレクティヴ」という切り口でも近年注目を集めています。しかし、彼らの「集まる」行為と集団への観念は、西洋概念の「コレクティヴ」が充てがわれる以前からそれぞれの文化的背景の中で培われてきたものではないか。このような問いが本書の取材の根底にあります。 〈YOKOKU Field Notes〉シリーズ第3段となる本書では、インドネシアにおける「集まり方の作法」をキーワードとして、美術家集団、森林レンジャー隊、メディア制作集団、「食」の在野研究集団という4つの活動を巡ります。ヴァナキュラーでありながら普遍性を内包する、インドネシア各地の集まり方を、個別の営みから見出す一冊です。 〈Jatiwangi Art Factory〉西ジャワ州・ジャティワンギ 瓦産業とアートを通じて住民の街づくりへの参加を促す美術家集団 〈LPHK Damaran Baru〉スマトラ島・アチェ州 コーヒー農園拡大のための伐採と対峙する、山間村落の女性たちによる対話型森林レンジャー隊 〈Videoge Arts & Society〉フローレス島 観光開発の煽りを受ける港町で”普通の住民”主体の街のあり方を探るメディア制作集団 〈Bakudapan Food Study Group〉ジョグジャカルタ 美術家と文化人類学者たちによる「食」の在野研究グループ 目次 概要 ・リサーチを紐解くキーワード ・リサーチの概要 本編 ・事例1:Jatiwangi art Factory 瓦職人が鳴らす公共圏の音色 ・事例2:LPHK Damaran Baru 森の中のコーヒートーク・パトロール ・事例3:Videoge Arts & Society “普通の住民”がつくるフェスティバル ・事例4:Bakudapan Food Study Group ポスト・ノンクロンの在野研究者たち コラム ・「集まり」を後押しする素地(廣田 緑) ・どっちつかずの私とあなたへ(北澤 潤) ・「集まり」それぞれの意味(廣田 緑) ・つきまとう家族主義からの脱出と対峙(西 芳実) 編集後話 〈YOKOKU Field Notes〉について 〈YOKOKU FIeld Notes〉は、コクヨが目指す「自律協働社会」の兆しを個別の地域から探索するヨコク研究所のリサーチ活動とそのレポートです。 同じ時代を異なる環境条件で生きる人々の中に身を投じ、聞き取りや観察を含むフィールドワークを通じてその営みの断片にふれることで、既存のシステムや規範をかいくぐるオルタナティブな社会のあり方を探り、また問い直すことを目的としています。 [書籍情報] 発行:コクヨ株式会社 サイズ:182mm×257mm ページ数:128ページ
-

煌めくポリフォニー わたしの母語たち|温又柔
¥2,420
[版元サイトより引用] 台湾で生まれ、日本で育った作家が、複数の言語のはざまに立ち、「正しい」「普通の」日本語を揺さぶりながら、言語の豊かさを紡ぎ出す。李良枝、呉濁流など、「国の周縁」で創作をしてきた先人たちの言葉に導かれ、日本語と向き合ってきた自身の軌跡をたどる。散文や講演録、創作を収めた、ポリフォニックな1冊。 目次 百年めの誓い 日本語のなかの何処かへ その1 宣戦布告 その2 私のものではない日本語 その3 独特の胸騒ぎ その4 舌の叛乱 その5 虐殺と言語 その6 「百年」の孤独 その7 もしも私が...... その8 たとえば彼女なら...... その9 思い出させる存在 その10 この名にちなんで その11 考える時間 その12 私たちが愉快でいられるために 付 録 引用出典に関するメモ 言葉の居場所を探して――李良枝再読のために ポリフォニーに還る 創作の中で煌めく〈真実〉 天皇のいなくなった国で、生まれて 「私」の小説 おてんきゆき あとがき 初出一覧 [書籍情報] サイズ:135mm×194mm 製本:上製 ページ数:182ページ
-

隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ|斎藤真理子
¥1,540
SOLD OUT
[版元サイトより引用] いま、韓国の文学、音楽、ドラマや映画に惹かれ、その社会や言語に関心を持つ人はますます増えている。本書では、著者が韓国語(朝鮮語)を学び始めた背景、この言語の魅力、痛みの連続である現代史と文学の役割、在日コリアンと言語のかかわりなどを、文学翻訳の豊かな経験から親しみやすく語る。文字、音、声、翻訳、沈黙など、多様な観点から言葉の表れを捉え、朝鮮半島と日本の人々のあいだを考える1冊。 目次 序に代えて――1杯の水正果を飲みながら 1章 말(マル) 言葉 韓国語=朝鮮語との出会い 隣の国の人々の「マル」 マルに賭ける作家たち 2章 글(クル) 文、文字 ハングルが生まれる 文字の中に思想がある マルとクルの奥にひそんでいるもの 3章 소리(ソリ) 声 豊かなソリを持つ言語 朝鮮語のソリの深さ 思いとソリ 4章 시(シ) 詩 韓国は詩の国 植民地支配の下で書いた詩人 現代史の激痛と文学 惑星のあいだを詩が行き来する 5章 사이(サイ) あいだ 翻訳の仕事をしている場所 サイにはソリがあふれている おわりに 韓国語と日本語のあいだをもっと考えるための 作品案内 [書籍情報] 著:斎藤真理子 装画:小林紗織 サイズ:130mm×168mm ページ数:160ページ
-

わたしの言ってること、わかりますか。|伊藤亜和
¥1,760
[版元サイトより引用] 新進気鋭の文筆家による、言葉にまつわるエッセイ集。セネガル人の父を持つ「ハーフ」ゆえに日本語に執着してしまうという著者。“それでも、私は日本語が好きだった。椎名林檎の歌が好きで、谷川俊太郎の「信じる」が好きで、男の人がふと漏らす「あら」の響きが好きだった。日本語は美しいと、感じることができる自分が好きだった”――残酷でやさしくて美しい言葉との邂逅を独自の視点ですくい上げ、唯一無二の世界を紡ぎ出す。 [書籍情報] サイズ:110mm×176mm ページ数:224ページ
-

差別はたいてい悪意のない人がする 見えない排除に気づくための10章|キム・ジヘ
¥1,760
[版元サイトより引用] あらゆる差別は、マジョリティには「見えない」。 日常の中にありふれた排除の芽に気づき、真の多様性と平等を考える思索エッセイ。 「日本語上手ですね」例えばそんな褒め言葉が、誰かに苦痛を与えることもある。多数者が変わらずに済むことを優先する社会は、少数者から「痛い」という言葉すら奪う社会でもある。これまでずっと無視してきた痛みに、私たち全員が向き合うための一冊。 ――望月優大(「ニッポン複雑紀行」編集長) 「細かいことで差別だ偏見だと騒ぐ人が増えて、なんだか疲れる」と思ったことはありますか。「騒ぐ人たちこそ、人を差別している」とも思うかもしれません。どうしてこんなに“窮屈な”世の中になってしまったのか? この本はそんな疑問に答え、頭を整理してくれます。 ――小島慶子(エッセイスト) 差別は日常的にある。いい人でも悪い人でも差別をしてしまう。偏った正義感こそが差別につながると、この本から学んだ。私は「差別があるのは仕方ない」と諦めるのをやめたい。まだ見たことのない、本当の公正な社会。それを目指す道すじをこの本が教えてくれる。 ――伊是名夏子(コラムニスト、車いすユーザー) 善意、不安、無知、無関心、被害者意識……と様々な形で「バランスの是正」や「差別の禁止」を阻んでいるマジョリティ〈多数派〉とはいったい誰なのか。認めるのは苦しいけれど、それはおそらく俺たちのことだ。 ――清田隆之(桃山商事代表) 目次 プロローグ あなたには差別が見えますか? I 善良な差別主義者の誕生 1章 立ち位置が変われば風景も変わる 2章 私たちが立つ場所はひとつではない 3章 鳥には鳥かごが見えない II 差別はどうやって不可視化されるのか 4章 冗談を笑って済ませるべきではない理由 5章 差別に公正はあるのか? 6章 排除される人々 7章 「私の視界に入らないでほしい」 III 私たちは差別にどう向きあうか 8章 平等は変化への不安の先にある 9章 みんなのための平等 10章 差別禁止法について エピローグ わたしたち 訳者あとがき 解説 韓国における差別禁止の制度化とそのダイナミズム(金美珍) [書籍情報] 著:キム・ジヘ 訳:尹怡景 サイズ:131mm×189mm ページ数:256ページ
-

現代思想2025年7月号 特集=バイスタンダーとは誰か 当事者/非当事者を問いなおす
¥1,980
[版元サイトより引用] 共感でも、同情でも、無関心でもなく 昨今、にわかに注目を集めるバイスタンダーという存在。いじめや差別の現場に立ち会ってしまったーー「当事者」ならざるーー第三者には、いかなる(不)介入が可能なのか。本特集では、そもそも当事者/非当事者が誰を指し示しているのかという問いにも立ち返りつつ、支援やアライの倫理、傍観者効果の問題など、多様な視座から「傍らに立つ者」のあり方やその葛藤について検討する。 目次 特集*バイスタンダーとは誰か――当事者/非当事者を問いなおす 討議 「ずるさ」からはじまるバイスタンダー考 / 石原真衣+西井開 ナラティブをひらく 愛がたどり着く場所――「母親」から「バイスタンダー」へ / 小西真理子 隣る人としてのレポレッロ / 奥村隆 「傍らに立つ者」の行方 傍観から援助へのグラデーション――傍観者は、当事者の助けになるのか? / 相馬敏彦 コミュニティは性暴力を止められるか? / 北風菜穂子 傍観者依存のいじめ対策を超えて / 山本宏樹 ポジショナリティから問う 身を守るための──あるいは、当事者にならないための──研究 / 朴沙羅 仁義と義憤と――なぜ私は「ひきこもり」に関わり続けるのか / 石川良子 憑依する人類学――「恨(ハン)」・シャーマン・バイスタンダー / 真鍋祐子 「共にある」ことを目指して バイスタンダー(傍観者)からウィズネス(共にある目撃者)へ――複数ルーツの人々への差別にどう向き合うか / 市川ヴィヴェカ+下地ローレンス吉孝 差別していないはずの自分の言動が差別的だと言われることによる困惑について――マイクロアグレッションの哲学的考察 / 池田喬+堀田義太郎 「私もあなたのアライになれますか」 / 森山至貴 バイスタンディング・マスキュリニティーズ――反フェミニズムと「新たな男性性」のゆくえ / 河野真太郎 誰が「当事者」なのか? 芸能界を変えるバイスタンダーの存在 / 森崎めぐみ メディアと当事者/性――東日本大震災をめぐる経験をもとに / 坂田邦子 社会運動を「立ち止まって見る」力――社会運動のバイスタンダーとしての社会運動論 / 富永京子 医療職と家族――安楽死の議論から漏れ落ちる「当事者」たち / 児玉真美 新連載●家族と憲法●第一回 憲法と家族法の関係 / 木村草太 連載●科学者の散歩道●第一一一回 一九七〇年代「バス通学」の蹉跌と「アメリカの夢」――バークレーのカマラ・ハリス / 佐藤文隆 連載●社会は生きている●第三五回 社会と自我11 ゲームと行為者(プレイヤー)――主体・未来・意志 / 山下祐介 連載●京都〈移民〉紀行●第七回 留学生のまち――教育移住とエスニックビジネスの集積 / 森千香子 研究手帖 揺らぐ「わたし」たちへ / 髙木美歩 [書籍情報] サイズ:144mm×221mm ページ数:230ページ
-

WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note
¥1,980
[版元サイトより引用] さまざまな角度から考える「声を聴くこと」 複雑化する世界をリサーチし、表象し、対話することの困難を見つめつつ、可能性を探る。人類学者達のノート論(足羽與志子/安渓遊地/大橋香奈/松村圭一郎)、哲学研究者・永井玲衣さんに教わる「人に話を聞く」5つのポイント、音楽家D・トゥープへのインタビューから、声を聞くこと・書き留めることを考えます。 目次 巻頭言 ノートという呪術 文=山下正太郎(WORKSIGHT編集長) スケーターたちのフィールドノート プロジェクト「川」の試み スケートボードの「声」をめぐる小史 文化史家イアン・ボーデンのまなざし ノートなんて書けない 「聴く・記録する・伝える」を人類学者と考えた 松村圭一郎・足羽與志子・安渓遊地・大橋香奈 人の話を「きく」ためのプレイブック 哲学者・永井玲衣とともに 生かされたレシピ 「津軽あかつきの会」の営み 野外録音と狐の精霊 デイヴィッド・トゥープが語るフィールドレコーディング それぞれのフィールドノート 未知なる声を聴く傑作ブックリスト60 ChatGPTという見知らぬ他者と出会うことをめぐる混乱についての覚書 文=山下正太郎 [書籍情報] 編:WORKSIGHT編集部 サイズ:152mm×224mm ページ数:128ページ
-

歴史修正ミュージアム|小森真樹
¥3,300
[版元サイトより引用] 排外主義と陰謀論が飛び交う欧米各地で出会ったのは、負の歴史を未来に語り継ぐための「修正」を実践する数々のミュージアムだった―― 戦争責任の軽視、植民地支配の正当化、差別の否認など、都合の悪い過去を好き勝手に書き換える「歴史否認」と、新たな史料や証言の発見や視点の拡張によって、過去を反省的に継承し、より多層的なものとして語り直す「歴史修正」。 ふたつの「修正」が対立する文化戦争の時代にあって、ミュージアムはいま「真実をめぐる語り」の土台を支える場となっている。わたしたちはいま、どのようにして歴史を語り直すことができるのか。1年かけて訪ね歩いた欧米各地のミュージアムから、現代社会を捉え直すフィールドワークの旅。 目次 はじめに 第一章 国の歴史を修正する 顔を描いて歴史を語る ロンドン 国を愛するアメリカ美術 フィラデルフィア アートが代わりに戦争する ヴェネツィア かえりみるキュレーション ヴェネツィア コラム 上流階級がアートで植民地主義批判 ロンドン 第二章 人種差別の歴史を修正する 植民地主義にツッコミを入れる スコットランド トカゲをジャマイカに返そう グラスゴー 現代アートの歴史修正主義 ロンドン カルチャーが再生するアフロ=カリブ系イギリス人の街と歴史 ロンドン コラム 死を展示する ニューオリンズ 第三章 性の規範を修正する ブラック・クィアの歴史を取り戻す ロンドン 娼婦博物館で知る“赤線地帯の秘密” アムステルダム ヴァギナ博物館のカウンターカルチャー ロンドン コラム 特許をアートし、憲法をエンタメする ワシントンD.C.+フィラデルフィア 第四章 階級を修正する ミュージアムのワーキングクラスヒーロー マンチェスター 課題を抱える地区にミュージアムをお届け フランス・イギリス各地 負け犬ロッキーが美術館と戦う フィラデルフィア コラム ミュージアムで働くプロジェクト ロンドン 第五章 みんなで修正する テンプルでフォーラムだ! マンチェスター 普段づかいのミュージアム マンチェスター 多様性のあるミュージアムとは何か? マンチェスター つくるを学ぶ子供博物館 ロンドン あとがき ミュージアムで、つながり、修正し、つづける [書籍情報] サイズ:128mm×188mm ページ数:304ページ
-

WORKSIGHT[ワークサイト]29号 アーカイブする?
¥1,980
[版元サイトより引用] なぜ残すのかを問い、過去と向き合い直す コクヨが制作中の「生活社史」を巡る岸政彦との対話、様々な企業による「仕事の蓄積、その方法と意味」、アーカイブ施設としての図書館の役割、「公共的な歴史と個人の記憶のあいだ」を揺れ動く複数のエッセイ、そしてブックリストまで。何を残すかではなく「なぜ残すのか」を問うことで、過去との向き合い方を改めて考える一冊。 目次 アーカイブ・オブ・モダン・コンフリクト 矛盾と混沌の実験室 800万点を超える古写真、1000万点を超える古文書やアーティファクト。時空を超えてロンドン某所に集められた「語られざる歴史」の断片は、現在を生きるわたしたちに何を語りかけているのか───蒐集の基準も目的もない。一般公開もしていない。驚異の「反アーカイブ」に潜入した。 〈アーカイブ・オブ・モダン・コンフリクト〉主宰のティモシー・プラスに聞く、選定基準も分類もないアーカイブの、その極意。 巻頭言 記憶のマネジメント 文=山下正太郎(本誌編集長) 社員の人生は社史になるか 岸政彦と語る、コクヨ「生活社史」という試み 現在、コクヨで「生活社史」という一風変わった社史編纂のプロジェクトが進行している。文房具、家具、オフィス設計など、小売から企業向けまでユーザーとの多様な接点をもつ企業の歴史を、販売店、社員、家族などとしてさまざまにコクヨと関わってきた個人の人生からまとめ直す試みだ。個人のライフストーリーを集め、それを企業のアーカイブとして編纂するとき、どんなことを考えなければいけないのか。 『東京の生活史』をはじめとする「街の生活史」プロジェクトの編者も務め、生活史という学問と手法を社会へとひらくアプローチを続ける京都大学・岸政彦教授を招き、「コクヨの生活社史」編纂室が聞いた。 企業アーカイブの現在地 仕事は流れ、そしてとどまる [ヤマハ/川島織物セルコン/ポーラ文化研究所] 日々の業務は流れ去っていくように見えて、企業の内側には確かに残るものがある。独自の価値観や働き方、そこから生み出されるプロダクトなどといった、企業の記憶。蓄積していく仕事のなかから、それをどう捕まえることができるのだろうか。ユニークな視点から、企業の記憶を捉え、アーカイブとして価値化する3つの企業を訪ねた。 21世紀の図書館のかたち スノヘッタ・人と知が出会う風景 図書館はもはや記録を保管するだけの場所ではない。オスロで設立され、現在では国際的な建築プロジェクトを数多く手掛けるスノヘッタは、アーカイブを「保存のための保存」から解き放ち、人と知が交わり続ける「生きた」存在として再定義する。2023年末に開館したばかりの北京図書館の設計を通じて描かれるのは、記憶を未来へと更新し続ける、21世紀のアーカイブのモデルケースかもしれない。スノヘッタのアジア統括マネージングディレクターであるリチャード・ウッドへインタビューを行った。 アーカイブの哲学 円城塔/ティム・インゴルド/今日マチ子/小原一真/藤井保文 国家や組織といった大きな歴史を形成するためだけにアーカイブが用いられた時代は終わり、人びとの記憶や声もまた保存の対象となった。公共的な記録と個人的な記憶の間を、現在のアーカイブは揺れ動いている。さまざまな分野の語り手たちが、それぞれの地点からアーカイブのあり方を見つめた。 独占か共有か、それが問題だ 情報学者・山田奨治と考えるデジタルアーカイブ デジタル技術の進歩により、知識や文化はかつてないほど自由にアクセスできるようになった。その一方、世界的に著作権の保護期間が延長傾向にあるなど、権利者による囲い込みも進んでいる。 『著作権は文化を発展させるのか:人権と文化コモンズ』などの著書があり、著作権制度の歴史と運用を分析してきた国際日本文化研究センターの山田奨治教授に取材した。文化の「公共性」を考えるとき、アーカイブはどのように保護され、ひらかれていくべきなのか。 ブックリスト アーカイブのアーカイブ 文書や声を集めて、取捨選択する。歴史を考証し、ときには偽る。アーカイブには、記録と記憶をめぐる人間の感情が縦横無尽に交錯している。アーカイブに対する語りを通して、わたしたちの欲望を覗き見る本のアーカイブ。 記憶の時代と感情の共有地 文=武邑光裕 テクノロジーの発展により、わたしたちの記憶はデジタル・アーカイブへと移行した。いま人間が担うのは、アーカイブを検索し、記録され得なかった感情を呼び起こすことなのかもしれない。そんな時代と呼応するように「みんなのきもち」という名のDJユニットが注目を集めている。 「記憶の時代」の新たな文化の姿とは。メディア美学者・武邑光裕による特別寄稿。 [書籍情報] 編:WORKSIGHT編集部 サイズ:152mm×224mm ページ数:128ページ
-

WORKSIGHT[ワークサイト]21号 詩のことば Words of Poetry
¥1,980
SOLD OUT
[版元サイトより引用] 社会のありようを異なる方法で示す言葉たち 詩のことばは、わたしたちの社会のありようを、異なる方法で指し示す。韓国現代詩シーンの第一人者へのインタビュー、ノーベル文学賞に輝いた詩聖・タゴールが愛したベンガルの滞在記、ハンセン病療養所の詩人たちをめぐる新作詩と随筆、銀行員詩人だった石垣りんから考える生活詩、建築家が語る詩集のデザイン、ことばの哲学者・古田徹也の思案など。 ページを開き、やがて閉じたとき、世界の手触りが変わっているかもしれない。 目次 巻頭言 詩を失った世界に希望はやってこない 文=山下正太郎(本誌編集長) 花も星も、沈みゆく船も、人ひとりの苦痛も 韓国詩壇の第一人者、チン・ウニョンが語る「詩の力」 ソウル、詩の生態系の現場より ユ・ヒギョンによる韓国現代詩ガイド そこがことばの国だから 韓国カルチャーはなぜ詩が好きなのか 語り手=原田里美 ベンガルに降る雨、土地の歌 佐々木美佳 詩聖タゴールをめぐるスケッチ 「言葉」という言葉も 大崎清夏 詩と随筆 ふたつの生活詩 石垣りんと吉岡実のことば 文=畑中章宏 紙の詩学 建築家・詩人、浅野言朗から見た詩集 詩人は翻訳する・編集する・読解する ことばと世界を探究する77冊 しっくりくることばを探して 古田徹也との対話・ウィトゲンシュタインと詩の理解 [書籍情報] 編:WORKSIGHT編集部 サイズ:152mm×224mm ページ数:128ページ
-

スマートシティとキノコとブッダ 人間中心「ではない」デザインの思考法|中西泰人 本江正茂 石川初
¥2,750
SOLD OUT
[版元サイトより引用] 発見的・開眼的に思考/試行せよ。 未来の都市像「スマートシティ」は、どのようにデザインされ、どのように人々に生きられるのか? 本書では、その構想のために「人類とは異なる知性の象徴としてのキノコ」と「人類を超越した知性の象徴としてのブッダ」を召喚。現在の人間と都市と社会を相対化し、人間中心「ではない」アプローチで世界を捉え直す探求の道を、地中と宇宙から照らし出します。 本書が提唱する思考法のポイントは、東洋/日本的な知のあり方である「無分別智」を身につけ、「今ここ、目の前にあるモノやコトの価値を新たに見出し(発見的)」、「その価値を別のところへ結びつけ、さらなる価値を生み出す(開眼的)」こと。さまざまな分野の先駆者たちとの対話を軸に、人間中心主義を超えるデザインのための理論、実例、練習問題を展開する一冊です。 対話編:久保田晃弘、豊田啓介、深澤遊、山内朋樹、石倉敏明、ドミニク・チェン、三宅陽一郎、ACTANT FOREST、津川恵理 目次 序章──スマートシティとキノコとブッダ 発見的・開眼的に創造する 人間中心主義を超えて──東洋的な思考を身につける 第1章 人間中心「ではない」デザインの思考法 理論編 1-1 問いと答えと、解き方の関係と順番 1-2 モノの価値を発見し開眼させる:ブリコラージュ 1-3 答えから答えが生まれる 1-4 受動的でありつつも能動的でもある 1-5 無分別智で新しい組み合わせを発見する 1-6 無分別智を繰り出す心と身体 1-7 無分別に発想する 1-8 無分別智と無心 第2章 人間中心「ではない」デザインの思考法 対話編 テクノロジーを/が生成する新しい人間 人智を超えたテクノロジーに向きあう 2-1 「スマートシティ」は人類の知性や徳を上げてくれるのだろうか? 中西泰人×本江正茂×石川初キックオフ鼎談 2-2 オルタナティブな知性に対する「想像力」と、人間中心主義を反転させる「デザイン」の可能性 ゲスト:久保田晃弘 2-3 情報の分解・編集から立ち現れる不可視のスマートシティ ゲスト:豊田啓介 2-4 キノコの知性、森の知性。人間の想像を超えた知のネットワークが都市のビジョンを変革する ゲスト:深澤遊 2-5 人はスマートシティにもパンジーを植えるのか? テクノロジーに飲み込まれた第三風景にも抗う「亜生態系」 ゲスト:山内朋樹 2-6 宗教と神話がつくり出してきた「ヒトと異なる知性」。ヒューマンセンタードを超えたワイズフォレストを求めて ゲスト:石倉敏明 2-7 「発酵」という世界の窓から覗く、人間と生物とロボットのいる生活風景 ゲスト:ドミニク・チェン 2-8 根っこを持った人工知能。スマートシティの下半分を考えていく ゲスト:三宅陽一郎 2-9 朽ちゆく「近代都市」をリ・デザインする。人と自然が共創する「食べられる森」 ゲスト:ACTANT FOREST 2-10 都市に生える場所 ゲスト:津川恵理 第3章 人間中心「ではない」デザインの思考法 実例編 3-1 チーバくん 3-2 壁の本 3-3 4分33秒 3-4 Lo-TEKとFAB-G 3-5 わらのワークショップ 3-6 スツールのバリエーション 3-7 百均造形 3-8 役に立たない機械 3-9 ファスナーの船とファンタジア 3-10 家具型ロボットFurnituroid 3-11 マイブームと民藝 3-12 東京R不動産と開放系技術 第4章 人間中心「ではない」デザインの思考法 練習編 4-1 デザインの思考法 #01 咄嗟の工作 4-2 デザインの思考法 #02 そそる謎メニュー 4-3 デザインの思考法 #03 ヒマワリゲリラ 4-4 デザインの思考法 #04 どこかの地面 4-5 デザインの思考法 #05 植物に名前をつける 4-6 デザインの思考法 #06 20倍の都市 4-7 デザインの思考法 #07 ゴジラになって都市に棲む 4-8 デザインの思考法 #08 鑑賞ガイドをつくる 4-9 デザインの思考法 #09 コーラを薄めながら飲む 4-10 デザインの思考法 #10 後ろ向きな絵手紙 4-11 デザインの思考法 #11 5年寝かそう 4-12 デザインの思考法 #12 21世紀が展示される博物館 4-13 デザインの思考法 #13 パンジーとして詠む 4-14 デザインの思考法 #14 レプリカントになってみる 終章──無分別智を共鳴させ縁起的な網を繕う 他者や他種と一緒に考える 考える都市の中で考える 偶然の網を紡いでいく 他力を受け入れ自力を超える 人間中心「ではない」デザインの思考法へ [書籍情報] 著:中西泰人、本江正茂、石川初 デザイン:福岡南央子(woolen) サイズ:148mm×211mm ページ数:360ページ
-

さびしさについて|植本一子 滝口悠生
¥902
[版元サイトより引用] ひとりだから、できること ひとりをおそれる写真家と、子どもが生まれた小説家による10往復の手紙のやりとり。 「折々のことば」にも取り上げられた自主制作本を文庫化。 母のこと、子どものこと、文章を書くこと、社会のこと、戦争のこと、過ぎ去った日々のこと。近所に住む写真家と小説家が、ときに応答しながら、親密な手紙を交わす。気持ちよい正直さと、心地よい逡巡にあふれるやりとりが、いつしか読者の記憶を掘り起こしていく。完売した自主制作本に、あらたな2往復のやりとりを加える。 目次 滝口さんへ 往復書簡をやりませんか? 一子さんへ 絵を習っていた話 滝口さんへ チャイルドシートを外した日 一子さんへ 思うようにならないこと 滝口さんへ 離ればなれになる道 一子さんへ 凡庸な感慨 滝口さんへ さびしさについて 一子さんへ 「み」の距離 滝口さんへ 誰かと一緒に生きること 一子さんへ 子ども?フ性別 滝口さんへ 最後に会ったのはいつですか 一子さんへ 家事について 滝口さんへ 母の言葉 一子さんへ 誰かに思い出される 滝口さんへ 誰かについて書くこと 一子さんへ ひとりになること 滝口さんへ いちこがんばれ 一子さんへ 愛は時間がかかる 滝口さんへ ひとりは、わるいものじゃないですね 一子さんへ 生活 [書籍情報] 自主制作版解説:武田砂鉄 文庫版解説:O JUN サイズ:105mm×148mm ページ数:256ページ
-

現代思想2024年6月号 特集=〈友情〉の現在
¥1,760
[版元サイトより引用] あいまいな〈友情〉のかたちを捉える 「家族」や「恋人」という枠組みには収まらないつながりが切実に考えられつつある今、〈友情〉はいかなる可能性もしくは問題を秘めているのか――。シスターフッドの再評価やホモソーシャルへの批判といった昨今の潮流に目を向けつつ、これまで見過ごされてきた関係のあり方や〈友情〉という概念そのものに正面から向き合いたい。 目次 特集*〈友情〉の現在 討議 すべてを「友情」と呼ぶ前に――名づけえないいくつもの関係 / 中村香住+西井開 今この場所でつながること 契ろう / 大田ステファニー歓人 「友達問題」と「推すこと」――好意の御しがたさ / 筒井晴香 共依存と友人関係――悩みの共有先としての身近な存在 / 小西真理子 友人関係と共同的親密性――「友人関係は結婚を代替し得るか」という奇妙な問いをめぐって / 久保田裕之 位置情報を交換する若者たち――友だちとの繋がり方 / 鈴木亜矢子 関係性の輪郭を探りながら ロマンチック・フレンドシップ・シンドローム / ひらりさ ポリアモリーと友情 / 深海菊絵 親密さの境界を問い直す――アセクシュアルとノンバイナリーからみる「恋愛/友情」の(不)可能性 / 佐川魅恵 往復書簡 ラブソングのその先へ――永遠不滅の友情を歌う / 児玉雨子+ゆっきゅん それぞれの友情のリアリティ そんなに友情を歌わせてどうする――合唱コンの卒業式化をめぐって / 森山至貴 バンドマンたちの友情のゆくえ / 野村駿 ホモソーシャルなつながりの周縁 / 沖縄ヤンキーの若者のしーじゃ-うっとぅ関係をもとに / 打越正行 ママ友は「仲良く」ケンカする――「保護者」と「友だち」の狭間の攻撃ストラテジー /大塚生子 友情のアルケオロジー 若者の友人関係とそのゆくえ / 浅野智彦 受験と「真の友情」 / 石岡学 いかにして「仲良し」は「尊い」ものになったか――テレビ・芸能にみる〝友情〟表象の過去、そして現在 / 太田省一 気づけば共に生きている 有償から始まる / 佐々木チワワ 非人間的友情という隘路――最小の友情、そしてダナ・ハラウェイ「かけがえのないタガい」 / 逆卷しとね 共に書く、友と書く / 山本貴光 連載●科学者の散歩道●第一〇二回 湯川のオッペンハイマーとの初邂逅――一九三九年のUCバークレー / 佐藤文隆 連載●「戦後知」の超克●最終回 見田宗介の「近代」と「現代」 13 / 成田龍一 連載●社会は生きている●第二二回 環境とシステム 8――言語の道具性――主体を動かす / 山下祐介 連載●現代日本哲学史試論●第六回 考える私の諸相――左近司祥子、鷲田清一、そして中島義道 / 山口尚 研究手帖 なぜ人は涙を流すのか / 石井悠紀子 [書籍情報] サイズ:144mm×221mm ページ数:248ページ
-

声を出して、呼びかけて、話せばいいの|イ・ラン
¥1,980
[版元サイトより引用] 血縁という地獄をサバイブしてきた。母は狂女になるしかなかったから、私もまた狂女に育った――。日本と韓国を行き来し、自由を追求する唯一無二のアーティストによる、渾身のエッセイ集。 死にたい時許せない時救われたい時、愛する人に会えなくなった時、私は死ぬまで何度もこの本を開くだろう。 ――金原ひとみ お母さんは狂ってて、お父さんはサイテーで、おばあちゃんは二人とも精神を病み、親戚はみんな詐欺師。そんな家族のもと、幼い頃から泣くことも笑うこともできず、いつも世界でひとりぼっちだった私が始めたのは、感情に名前をつけること――。 1986年生まれ、日本と韓国を股にかけて活躍するミュージシャン・作家・エッセイスト・イラストレーター・映像作家のイ・ランによる、「これまでの家族」と「これからの家族」。 日韓同時発売。 目次 体が記憶している場面たち 母と娘たちの狂女の歴史 本でぶたれて育ち、本を書く お姉ちゃんを探して――イ・スル(1983.11.03 〜2021.12.10) 三つの死と三つの愛 ダイヤモンドになってしまったお姉ちゃん お姉ちゃんの長女病 ランは早死にしそう 私の愛と死の日記 すべての人生がドラァグだ お姉ちゃんの車です 死を愛するのをやめようか 今は今の愚かさで あなたと私の一日 この体で生きていることがすべて 1から不思議を生きてみる イ・ランからジュンイチへ ジュンイチからイ・ランへ 確かな愛をありがとう [書籍情報] 著:イ・ラン 訳:斎藤真理子、浜辺ふう サイズ:128mm×188mm ページ数:208ページ