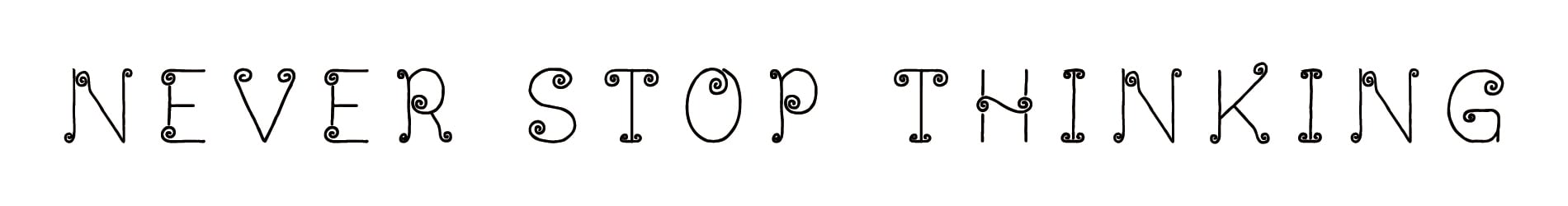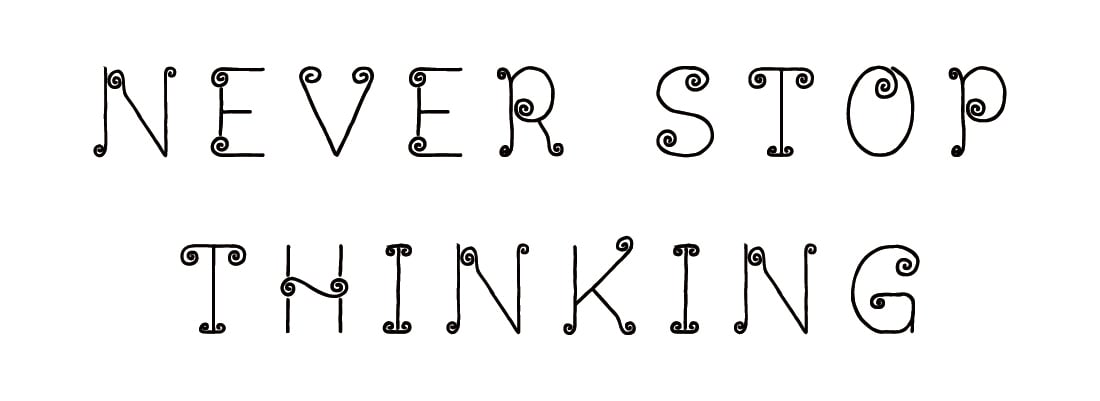Mail magazine
NEVER STOP THINKINGの選書担当が、店番中に本を読みながら考えたことを書いています。不定期配信。
Mail Address
Sample
2025.08.25 『半分姉弟』『差別はたいてい悪意のない人がする』
ずっと気になっていた『半分姉弟』の1巻を読みました。
「ハーフ」と呼ばれてきた人たちと、その周りで暮らしている人たちの群像劇。どこにでもいそうな普通の人たちの日常で、その普通さが描かれることで、現実がより際立ち、自分の身のまわりと重ね合わせやすくなるように感じます。
本作の冒頭では、作中で用いられる「ハーフ」の意図が注意書きとしてしっかり書かれています。
東京都人権啓発センターのホームページに掲載されている記事(※1)によると、「ハーフ」は「半分」という意味で、一般的には父母のどちらかが外国籍という国際結婚で生まれた子どもが「ハーフ」と呼ばれるそうですが、これは日本でしか通じない和製英語で、なおかつ、こうした一般的な場合には含まれない条件も多々あり、明確な定義があるわけではないそうです。戦後から現在まで、社会的には肯定的にも差別的にも扱われてきた歴史があり、「ハーフ」に代わる呼称として「ダブル」や「ミックス」などの言葉も新たに登場したものの、その範囲や意味合いなどはさまざまで、当事者の中でもこれらの呼称を肯定的に用いる場合もあればそうではない場合もあるそうです。
こうした歴史的な流れもあり、「ハーフ」という呼称の意味合いに傷ついてきた当事者の方は多く存在しており、今でも議論が続いていることから、本作では、この呼称について改めて読者に問い直したいという著者の意向(※2)で、タイトルに「半分」という言葉がつけられ、作中にも「ハーフ」という呼称があえて用いられています。
登場人物は、それぞれがそれぞれの個別具体の地獄を抱えながらなんとか生き延びてきていて、この国で「ハーフ」と呼ばれてきた人たちが経験してきたであろう人種差別を受けずに済んできた自分は、そのような苦しみをつくる側に回ってしまう可能性について考えながら読まざるを得ない内容でした。
差別に対して反対の意志があったとしても、「自分は絶対に差別をしない」と断言することは難しい。それは、差別を差別として認識できていない自分自身の無知さや、過去に受けた教育や触れてきたメディアなどで培われてしまった無自覚や無意識の偏見が自分の中には少なからず存在しているからだと思います。それでも、見ずに、知らずに、気がつかずに済んできたことに対して自覚的になりたいです。
そして、『半分姉弟』を読んだ後は、『差別はたいてい悪意のない人がする』を読みました。いいタイトルですね。著者のキム・ジヘさんは、学生時代の頃から障害者の権利を学んだり法律の授業を受けたりしながら人権について学び、その後も韓国のさまざまな差別問題に関心を持ちながら当事者へのリサーチや政策提言に携わってきたそうです。こうやって略歴が書かれると、著者は差別をする側にはなりづらそうですが、とあるシンポジウムに登壇した際、著者自身が差別的な発言をしてしまったことがあったという経験から、本書は執筆されました。
この本では、女性、障害者、セクシュアル・マイノリティ、移民などに関する事件や論争を題材にしながら、悪意なき差別が生まれてしまう背景や、差別が不可視化される構造が説明されています。マジョリティ側が自分たちの特権に気がつきづらい理由、マジョリティとマイノリティという線引きの難しさ、人は性別、国籍、職業、性的指向など複数の属性を持つからこそ、差別を一つの軸から眼差すには困難があることなど、差別や不平等の問題について考える上で、知っておくべきであろう視点がたくさん語られています。たとえば、本書に書かれていた以下のような指摘は、これまでマジョリティ側に立っている状況が比較的多かった自分としてはかなり耳が痛いものであると同時に、しっかり自覚しなければならないことでもあると感じました。
不平等と差別に関する研究が進むにつれ、学者たちは平凡な人が持つ特権を発見しはじめた。ここで「発見」という言葉を使ったのには理由がある。このように日常的に享受する特権の多くは、意識的に努力して得たものではなく、すでに備えている条件であるため、たいていの人は気づかない。特権というのは、いわば「持てる者の余裕」であり、自分が持てる側だという事実にさえ気づいていない、自然で穏やかな状態である。
『差別はたいてい悪意のない人がする』P.30より
私は日本で生まれて日本で育ち、中学から大学まで私立の学校に通っていました。男性として生まれ、今の時点では性自認も男性の異性愛者です。これらの属性だけでも、現在の日本社会では差別的な言動や発言が向けられづらい環境の中、とてもたくさんの特権を持った状態で生活しています。
なぜ、このような自分の立場は特権を持つ側だとわかったのか。それは言葉にすると陳腐ですが、やっぱり他者を知ることを通してだったんじゃないかと思います。本を読んだり人と話したりすることで、完全に他者になることはできずとも、それでも他者の視点を借りながら、自分と他者が暮らしている社会という地面が水平になっていないことを発見しました。
社会にあるさまざまな仕組みはマジョリティ中心につくられていることが多く、だからこそ特権を持つ自分は社会に対してそれほど不自由を感じないまま、先ほどの引用文にもあるような「自然で穏やかな状態」で、それなりに生活ができていたという事実が徐々にわかってきました。
社会の構造的な差別に気づくためには、まずは自分の立場を知る必要があると思いますが、普段の生活の中で、当たり前に慣れ親しんできた自分の立場というものを捉え直すことは、なかなか難しい。それでも、誰かの立場を知ることを通してであれば、相対的に自分の立場もわかるようになり、そうすると自分には見えていなかった死角にも気づけて、徐々に差別の構造が見えてくるようになると思います。
参考
※1 「ハーフ」と呼ばれる人々|公益財団法人 東京都人権啓発センター
https://www.tokyo-jinken.or.jp/site/tokyojinken/tj-81-feature.html
※2 藤見よいこさんが『半分姉弟』で描く「ハーフ」と呼ばれる人々の違和感と希望【マンガが生まれる場所 vol.22】|yoi(ヨイ)
https://yoi.shueisha.co.jp/body/culture/9876/
2025.08.15 『デザインはみんなのもの』
ミスフィッツ(はみ出し者)のストーリーを伝える出版スタジオ〈Troublemakers Publishing〉のブックレーベル〈Misfits Books〉から入荷した『デザインはみんなのもの』を読み進めていて、今回はこの本について書いてみます。
この本は、スイスを拠点に、フェミニズム、デザイン、政治に関するオンラインプラットフォームを運営している〈Futuress(フューチャーレス)〉が、これまでに掲載してきたおよそ140本の記事の中から、5本を抜粋・翻訳したエッセイ集です。トルコ、ノルウェー、アメリカ、インド、パレスチナの書き手たちが、フェミニストの視点を通して各地のデザイン業界の「当たり前」に潜むゆがみを批評し、世界をフェアなものに立て直していくための道筋を読者に示します。それぞれの書き手たちが綴る各国の現状は、遠くの場所で起きていることではなく、日本のそれとも重なる部分が多いです。
特に印象的だったのは、パレスチナのヴィジュアルアーティスト・独立研究者のノウラ・タフェチェさんの「パステルカラーの暴力」。日本が世界を魅了し続けているカワイイカルチャーの特徴である、親しみやすさや可愛らしさが、暴力を覆い隠すものとして機能してしまっている実態を書いたエッセイです。
アニメや漫画にとどまらず、ゲームやファッションなどとも密接に絡まり合うカワイイカルチャー。「カワイイ」は〈kawaii〉として世界からも認識され、注目を集めていることは、直接的にデザイン業界に関わっていない人でもなんとなく聞いたことがあるかと思います。一方で、このカルチャーの影響を受けたアニメ、漫画、ゲームのようなコンテンツの一部では、主に女性キャラクターの人物表象において露骨な性描写などが多く見受けられ、それは現実の暮らしに残った古めかしいジェンダーロールを助長するものとして問題視されている側面もあります。
そして近年、カワイイカルチャーは二次元や空想の域を越え、武器や兵器などのデザイン、さらには女性の見た目をした兵士を写したソーシャルメディア上における軍のイメージ戦略など、現実の世界に存在している暴力を巧妙に隠蔽するものとして使用されています。エッセイの後半では、カワイイカルチャーが持つ特徴を悪用した、イスラエル軍のプロパガンダが紹介されています。
イスラエルは、LGBTQ+の権利尊重をアピールしながら国際社会に対して自国のイメージアップをはかろうとしている一方で、パレスチナへの入植をやめないというダブルスタンダードを続けています。このエッセイを読んで初めて知ったのは、たとえばTikTokでは女性の見た目をした国防軍の兵士たちが、猫耳のコスプレでのポージングや過剰に性的な表現などを投稿していて、SNS上における視覚デザインを使って人々の目を欺き、植民地主義を隠蔽しようとしているということでした。
人が抱えているネガティヴな感情を癒してくれるようなカワイイはたしかに存在するし、そこにケア的な効用や期待も少なからずありますが、このようなプロパガンダに利用されるようなことはあってはならないと思います。
このような事例に限らず、自分が日常的に触れている何気ないデザインを、ただ無心に受け取るだけではなく、時には批評的に見てみることが必要だと感じました。たとえば、日本は欧米の文化に影響を受けてきたという歴史的な背景がある国で、ファッション雑誌のようなメディアでは、欧米のトレンドの模倣のようなものが続いています。それらのメディアでは白人か、あるいは白人にルーツがあるように見えるモデルが起用されていることが多く、そういったモデルの採用なども含めたメディアのデザインは、意図せず白人至上主義に加担してしまう恐れがあるんじゃないかと感じます。
今でも続く、人種に優劣をつける思想やそれを理由にした差別や迫害と、生活の中にある何気ないデザインはつながっている。そのことに気がつくと、どこから見ても完璧なデザインを目指すことの困難さはあるにせよ、それでもデザインをつくる側と受け取る側には、それぞれの立場からよりよいデザインについて考えることができるはずです。専門家やデザイナーではなくとも、というか、そうではない立場だからこそ気がつくこともきっとあって、暴力や差別をなくすために、このような視点からも対話を始めてみることが大切だと思います。